|
何をいまさら構造力学・その 4 ― 座屈 ―
今回は「座屈」、つまり「軸力によって生じる曲げ変形」を取り上げることにします。
計算規準にある計算式には意味がよく分からないものが多々ありますが、「座屈を考慮した許容圧縮応力度」はその最たるものかもしれません。そもそも、座屈の計算式の中に円周率 π が登場するはなぜなのか ? その理由を知る人は案外少ないような気がします。
座屈を考慮した許容圧縮応力度
座屈とは、棒状の物体をその軸方向に押し込んだ時、それが「縮む」かわりに「曲がって」しまう現象のことを指します。それにしても、なぜ「そういうこと」が起きるのか?
もし、その物体が「完全にまっすぐ」で、その組成が「完全に均質」で、かつ作用する力がその物体の中心軸に正確に合致していたならば、その物体は「縮む」はずです。理論的には「曲がる」はずがない。
しかし、私たちはそれが「曲がる」ことを経験的に知っています。
それはなぜかというと、「完全にまっすぐ」で「完全に均質」な物体というものは、実際にはありえないからです。たとえば私たちは「柱がまっすぐに立っている」ことを前提として構造計算を進めるわけですが、実際には不可避的な「曲がり」( 元たわみ ) は必ずあるものと考えておかなければなりません。しかし容易に想像できるように、それが「どれくらいまっすぐか」「どれくらい均質か」を数値的なファクターとして計算に組み入れるのは難しい。
そこで座屈荷重――その物体に座屈現象を生じさせるような荷重の大きさ――を数値的に定める際には、純粋な理論値だけでなく、そこに何らかの「安全率」を加味しないわけにはいかなくなるのです。
日本建築学会「鋼構造許容応力度設計規準」にある「座屈を考慮した長期許容圧縮応力度 fc 」の計算式を下図の左に掲げました。さらに右側には、fc と細長比 λ ( 小文字のラムダ ) ――この値が大きいほど部材が細長く、座屈を起こしやすいとされる無次元数――と fc の関係をグラフにあらわしてあります。
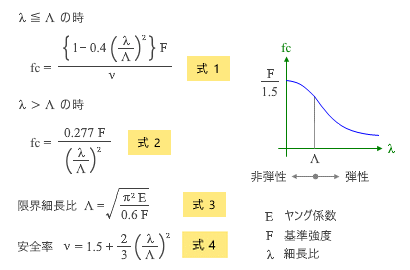
ここにある通り、fc の値は限界細長比 Λ ( 大文字のラムダ ) を境として切り替わります。λ が Λ を超えて 式-2 が適用される領域を 弾性座屈 または オイラー座屈 注 )、式-1 が適用されるそれ以外の領域を 非弾性座屈 と呼んでいます ( ちなみに実際の Λ は 100 強程度の値になる ) 。
注)
レオンハルト・オイラーはスイスで生まれた 18 世紀の大数学者で、アイザック・ニュートンの一世代ほど後にあたる。
読んで字のごとく、「弾性座屈」とは応力度が弾性範囲内にある時のもの、「非弾性座屈」とは応力度が弾性範囲を超えた時のものです。ただし、ここでいう「弾性範囲を超えた」は「降伏点を超えて塑性化した」とは違います。これは「応力度とひずみ度の比例関係 ( フックの法則 ) が成立する限界を超えた」という意味です。
私たちは「応力度 σ とひずみ ε は弾性範囲内 ( σ が降伏応力度 σy より小さい ) において比例関係にあり、その直線の勾配がヤング係数 E である」ことを知っています。もちろん、通常はこれで十分なのですが、しかし厳密にいうと、σ が σy に至るまで完全な直線をなしているわけではありません。
下図のように、応力度が σy に達する手前でグラフが「おじぎ」をし始めるのですが、その境界点が 比例限度 σp です。この図から分かるように、ここを超えるとヤング係数は初期状態よりも小さくなり、したがって弾性理論に基づいた「弾性座屈」の式が適用できなくなってしまう。ここから先が「非弾性座屈」です。
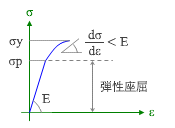
さて、これから 式-1 から 式-4 までの各式を吟味して行くことにしますが、そのためには、まず ( 実務上の「安全率」が勘案される前の ) 「純粋な理論式」を知っておく必要があります。しかし実は、そのようなものがあるのは「弾性座屈」の方に限られます。「非弾性座屈」の方は種々の実験等をもとに決められた近似式ですので、これについて詮索してみても仕方がありません。
弾性座屈の理論式とは下のようなものです ( なおここでは、前記の許容応力度 fc の代わりに座屈応力度 ( 座屈を生じさせるような応力度 ) σ、基準強度 F の代わりに降伏応力度 σy を使っているが、基本的には同じ ) 。
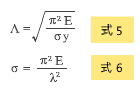
式-6 の σ と λ の関係をグラフにあらわしたのが下図左です。
この式とグラフを見ていただければ分かるように、λ の値が 0 に近づくにつれて σ の値は無限大に近づく。しかし、これはあくまでも弾性理論に基づいた式ですから、σ が降伏応力度 σy に達するまでが適用範囲で、それ以外の部分 ( グラフ上の破線 ) は信用できません。この境界点こそが 式-5 で得られる限界細長比 Λ なのです。
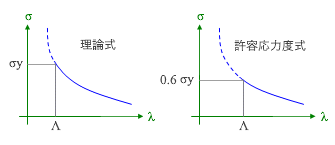
ただし実用設計上、この理論式は二つの点で都合が悪い。
一つは、座屈理論がどうであれ、とにかく許容応力度は σy / 1.5 ( = F / 1.5 ≒ 0.67 × F ) を超えてはいけない、という制約。そしてもう一つは、実際の材料は降伏応力度 σy に達する前、つまり比例限度 σp に達した段階で弾性理論が成り立たなくなる、という事実です。
そこで理論式に何らかの操作を加える必要が出てきたのですが、それが何だったのかは 式-5 と 式-3 を比べてみれば一目瞭然でしょう。式-5 にある 0.6 という数値がその役目を担っているのです。
これはようするに「圧縮応力度が基準強度 F ( = 降伏応力度 σy ) の 60% に達した時点を弾性限度としよう」という意味です。上図右のグラフに見るように、この操作は限界細長比 Λ の位置を右に移動し、弾性座屈の適用範囲を狭めることに相当します。
これがなぜ「安全率」になるのかというと、一つには、実際の比例限度は 0.8 × σy 程度であると考えられていることです。そしてもう一つは、この 0.6 という数値は実質的に許容圧縮応力度を低減する効果をもたらすためなのですが、これについて説明します。
式-2 と、その元になる 式-6 を見比べてみてください。
だいぶ様相が違ってますが、説明の都合上、まず 式-6 を安全率 ν ( とりあえず 1 とする ) で割っておき、さらにこの分母と分子を Λ2 で割ると下の 式-7 が得られます。
ここにある σy を F に読み替えれば、これが実質的に 式-2 と同じものであることが分かるはずです。そして 式-2 にある 0.277 という奇妙な数字が安全率 ν に関わっていることも何となく察しがつくでしょう。
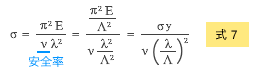
そこで、今度は逆に 式-6 を変換して 式-2 の形にしてみると下のようになります。 注 )
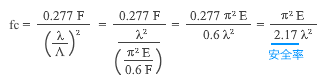
注 )
ご覧の通り、式の変換の途中で基準強度 F の値が消去されてしまいます。式-2 の中に基準強度 F という値が入っているので思わず勘違いしてしまいますが、式-6 の理論式から分かるように、弾性座屈領域における fc の値は F に依存しません。材質が何であれ同じ値をとるのです。
これを 式-7 と見比べれば分かるとおり、弾性座屈による許容圧縮応力度の安全率は 2.17 になるのですが、それにしても、この数字の「中途半端さ」は不可解です。
学会規準の解説その他には安全率 2.17 という記述はあっても、その根拠は書かれていません。したがって自分で考えるしかないのですが、この値は以下のように分解することができます。
安全率 ν = 2.17 = 1.5 + 1.67 - 1.0
最初の 1.5 が「長期許容応力度の安全率」で、これはご存知の通り。であるならば、2番目の 1.67 は「座屈に関する安全率」のはずです ( 最後に1を引いているのは、右辺の第1項・第2項で1が重複しているため ) 。
ところで、式-7 の分子にある σy を比例限度 0.6 × σy に置き換えれば、この時の安全率 ν は 0.6 の逆数 1.67 です。結局、これが上記の「座屈に関する安全率」に相当すると考えればいいのでしょう。
このことは非弾性領域の安全率をあらわす 式-4 からも確認できます。この式の第2項の 2/3 は 0.67 ですから、ここに λ = Λ という条件を入れて限界細長比を計算すると 2.17 という同じ数字が得られます。 注 )
結局下図のように、安全率 ν の値は、非弾性座屈の領域では λ の2次関数、弾性座屈の領域では一定値 2.17 をとるのです。
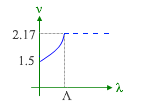
注 )
これは「長期」の許容応力度だが、「短期」の方はこれを単純に 1.5 倍してよいことになっている。するとこの場合の安全率は 2.17 - 1.5 = 1.67 ではなく、2.17 / 1.5 = 1.45 になってしまう。長期・短期に関わらず比例限度として 0.6F という値を使っていることからすると、ここには矛盾があるような気もする。このあたりの事情はよく分からないが、「設計上の簡便さ」を優先させた結果なのかもしれない。
話の順序が前後してしまいましたが、次項では、上に掲げた理論式の成立過程を見ていくことにします。
| 1 | 2 | 次へ
|