崩壊時の外力分布
話を簡単にするために、前章の例題の図はすべて平屋の建物を対象にしていました。このような建物では、ただ単純に、作用させた地震力 P の倍、α・P が保有水平耐力になります。
これが 2 階建て以上の建物になるとどうかというと、下図にあるように、地震力は各階の床に作用する P1, P2, P3 ・・・ の集合になります。これをベクトル表示すると { P } ですが、この表現を使えば、保有水平耐力は α { P } です。
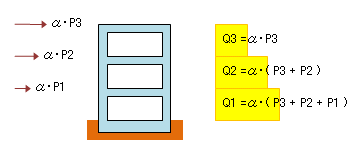
つまり、P1, P2, P3 ・・・ の比を一定に保ったまま力を漸増させていく(当然ながら、それらによって各階に生じる層せん断力も一定の比を保って増加する)わけですが、この「一定の比を保ったまま」という点が、じつは、とても重要です。
なぜかというと、増分解析法の「増分」の中には、「作用する複数の力が一定の比を保ったまま増加するとしたならば・・・」という意味が込められていて、それこそがこの解析法の「かなめ」だからからです。
「比例的に増加しない力」の前では、増分解析法という武器は役に立ちません。
(なぜそうなのか、という説明は省略しますが、増分解析法についてもう少しくわして知りたい方は、「限界耐力計算って何だろう?」 をお読みください。)
建物に作用する地震力は上の階にいくほど増幅され、大きくなります。そして、増幅される度合いは、建物が柔らかい(固有周期が長い)ほど大きくなります。これは、告示の式をまつまでもなく、「柔らかいものほど先端が大きく揺れる」という日常的な経験から理解できます。
一方、建物の崩壊とは、建物のあちこちにヒンジが形成されていくプロセスです。これはすでに言いました。そして、ヒンジとは「関節」で、そこに何がしかの「回転能力」が生まれる、ということも言いました。
その結果どうなるのかというと、
建物にヒンジが形成される過程で建物はどんどん柔らかくなり、それにつれて地震力の増幅度が大きくなり、その分布形がトップヘビー(上にいくほど大きい)になる
のです(図示すると下のとおり)。
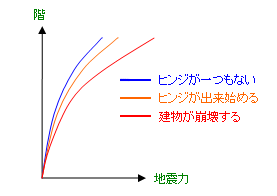
でも、これはたいへん困ります。増分解析法では、地震力は「一定の比を保ったまま」増加しなければならないのです。
そこでどう考えるのかというと、「私たちは建物が崩壊する時の状態を知りたいのだから、崩壊時点、あるいはその近辺の地震力の分布(上の図の赤い線)を最初から作用させるのがよかろう」となります。
となると次は当然、「建物の崩壊時点の地震力の分布とはどのようなものなのか」ですが、じつは、これがよく分かりません。というか、私は研究者ではないので、そういうことを断定的に言える立場ではありませんが、少なくとも今のところ、私たちは、それを簡便にもとめるアルゴリズムを目にしてはいません。
増分解析法とは、地震力という原因から建物の崩壊という結果をもとめるものです。原因、つまり初期条件が変われば、当然その結果も変わってきます。ですから、これを「よく分からない」で済ましておくわけにもいかないのです。
そこで、 2007 年に公布された国交省告示 594 号第 4 に以下のように記されることとなりました。
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合にあたっては、建築物の地上部分の各階について標準層せん断力係数の数値を漸増させ、これに応じた地震層せん断力係数に当該各階が支える部分の常時荷重を乗じた数値を水平力として作用させるものとする。この場合において、当該地震層せん断力係数を計算する場合に用いる Ai は、令 88 条第 1 項に規定する Ai を用いなければならない。
一次設計(弾性設計、つまりヒンジが一つもない状態をターゲットとするもの)用の地震力の分布を、そのまま二次設計(弾塑性設計、つまりヒンジ発生後の状態をターゲットとするもの)用として使いなさい、あるいは使ってよろしい、と言っているのです。
しかし、ここでまたしても疑問がわいてきます。
・・・ Ai からもとめられる地震力とは、そもそも、建物がどのような状態にある時をターゲットとしたものなのか?
考えられる答えの一つは、「これは建物の弾塑性時をターゲットとしたもので、それを一次設計にも流用している」であり、もう一つは、「これは建物の弾性時をターゲットとしたもので、それを二次設計にも流用している」です。
そのどちらかのはず、と私なんかは考えてしまいますが、しかし、技術基準解説書にある以下の記述(P.306)を読むと、じつは、そのどちらでもないようなのです。
地震時に、建築物のある階が崩壊するときの外力分布がどのようなものであるかを特定することは難しい。その一方、建築物が弾性域にある状態及び部分的又は全体的に塑性域に入って崩壊に近いほどの大きな変形に達した状態等における外力分布については数多くの地震応答結果が蓄積されており、それをまとめたものが Ai 分布にもとづく外力分布である。
「・・・は難しい。その一方、・・・」の「その一方」のニュアンスはかなりデリケートですが、これを、私なりの理解にもとづいて翻訳すると次のようになります。
Ai の計算式とは、多くの建物の強震時の応答結果の集積から回帰的に得られたものである。
このサンプリングには、強震時に弾性域内にある(一つのヒンジも生じない)ものから、多くのヒンジが生じて崩壊に近い状態のものまでが幅広く含まれている。
Ai とは、それらを全部ひっくるめた「大づかみの傾向」をあらわしたもので、とくに弾性とか塑性とかを意識したものではない。
だからこの値は、一次設計にも使えるし、二次設計に使えるのである。
あるいは、もう少し補足すると、
たしかに、建物が弾性状態にある時と崩壊に近い状態にある時では地震力の分布が変わってくる。
しかし、その違いは、Ai という値が本来持っている「誤差」の中に吸収できる程度のものである。
ということなのかもしれません。
さらに、技術基準解説書のさきほどのページには、保有水平耐力算出時の外力分布として「 Ai にもとづく外力分布」注) の採用をすすめるもう一つの理由として、「必要保有水平耐力 の算定にもこの値が使われているから」ということがあげられてています。
注)
告示の表現では「 Ai 分布にもとづく外力分布」ですが、まどろっこしいので、以後は「 Ai にもとづく外力分布」ということにします。それにしても、もう少し簡潔な用語を工夫していただけないものでしょうか?
「建物に作用する地震力の分布形」という概念は、現行の構造計算では、「一次設計」「保有水平耐力」「必要保有水平耐力」という 3 つのステージで使われます。そして、そのすべての局面で同じ分布形を使うというのは、たしかに最もスジが通るし、何よりも「分かりやすい」と言えます。
どういうふうに分かりやすいのかというと、これにしたがえば、「保有水平耐力は一次設計の地震力の X 倍であり、かつ、必要保有水平耐力の X 倍である」というふうに簡潔にあらわすことができるのです。
「 Ai にもとづく外力分布」とは、「崩壊時の外力分布」という本当のところはよく分からないものに対する最も分かりやすい答えです。特別な理由がない限り、これにしたがっておくべきでしょう。
それから、さっそく補足しておかなければなりませんが、さきほど、「保有水平耐力は必要保有水平耐力の X 倍である、というふうに簡潔にあらわすことができる」と言ったのは、各階の 構造特性係数 と 形状係数 がまったく同じ場合に限られます。これが各階で異なると、この X 倍の値も各階で違ってしまう。つまり、保有水平耐力と必要保有水平耐力の関係がデコボコになります。
技術基準解説書のさきほどのページによると、このような場合には、保有水平耐力の外力分布として「必要保有水平耐力にもとづく外力分布」を使ってもよい、とされています。この考え方の根拠になっているのは、「必要保有水平耐力とは、強震時の建物の層せん断力の応答値そのものと見なすこともできる」という考え方だと思いますが、さて、どんなものでしょうか。
これはヘタをすると、「もともとよく分からないものによく分からない補正を加えてさらに分からなくする」ことにもつながりかねないのではないか、と私は懸念します。
