構造特性係数
構造特性係数 Ds は建物の変形能力を数値化したもので、変形能力が高いほど小さくなり、その効果として、要求される保有水平耐力の水準(必要保有水平耐力)を押し下げることができる、というのが前章の内容でした。
しかし、「建物の変形能力」といっても、いたって話はバクゼンとしています。
そこでどうするのかというと、まず、建物を構成する個々の部品、つまり柱とか梁とかの「部材」に注目します。
それらの特性を一つ一つ調べ上げ、変形能力が高いと思われるものから順に A, B, C という「格付け」を行う。そのランキング(「部材ランク」あるいは「部材種別」と呼ばれる)を集計した上で、最後は「多数決の原理」にしたがうことにする。
つまり、「変形能力の高い部材で構成されている建物ほど変形能力が高いはず」と考える。
・・・ごく大雑把にいえば、構造特性係数を定める手順とはこのようなものです。
さて、いたってプリミティブな話から入りますが、柱なり梁なりの「部材」をさらにつきつめると、結局は鉄なりコンクリートなりの「材料」に行き着きます。そして、これらの材料の力学特性(力と変形の関係)とは以下のようなものです。
材軸方向に加えた力が小さく、弾性限界を超えるまでは力と変形は比例関係にあり(フックの法則)、元に戻ろうとする力(復元力)を持つが、弾性限界を超える(塑性化する)と復元力が失われ、小さな力が大きな変形を生み出すようになる。つまり、力と変形の関係をあらわすグラフが「横に寝てくる」。
そして最大耐力に達した後、変形が増大し、やがて、壊れる(「破壊」あるいは「破断」と呼ばれる)。
材料による微妙な差異はありますが、その様子をごく図式的にあらわすと下のとおりで、塗りつぶした部分が「エネルギー吸収量」です(ようするに、今までさんざん出てきた「建物の力と変形の関係」とおんなじです)。
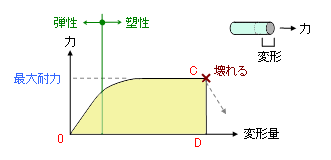
「建物が崩壊していく過程で部材端にヒンジ(関節)が生じ、それによって一定の回転能力が生まれる」ということを何度か言いましたが、この現象の元となるのは「曲げモーメント」という力です。
ご存知のとおり、曲げモーメントは「材軸方向に作用する、同じ大きさを持ち、かつ作用方向が反対な 2 つの力(偶力)が一定の距離をおいて作用する」ことにより生まれます。ですから、この「材軸方向に作用する力」が上のような特性にしたがうのであれば、下図にあるように、曲げモーメントと変形(この場合は曲げによって生じる「回転角」を指す)の関係も同様の特性を持つはずです。
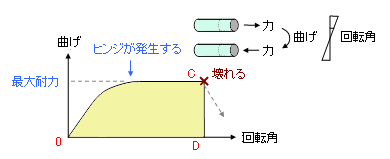
ヒンジによって「回転能力が生まれる」のは、このグラフが「横に寝てくる」ことの結果ですが、ここで重要なのは、
グラフが水平に近くなってから「壊れる」にいたるまで、部材が一定の耐力(曲げ)を保持したまま変形が進行する
という事実です。
これは曲げモーメントを原因とする壊れ方なので「曲げ破壊」といわれます。
上の図から分かるように、この壊れ方は材料が本来持っている力学特性に忠実で、変形に追随する能力が高いので、「粘りがある」という意味から「靭(じん)性破壊」と呼ばれます。
その反対は「粘りがない」「脆(もろ)い」で、これは「脆(ぜい)性破壊」です。
これは、材料が本来持っている変形能力をフルに発揮する(つまり上図の C 点に達する)前に壊れてしまう状態を指し、その典型的なものとして「せん断破壊」「付着破壊」「局部座屈破壊」などが挙げられます。
当然ながら、「靭性破壊は好ましい・脆性破壊は好ましくない」とされます。前に、「部材に(曲げ)ヒンジが発生して建物が壊れていくのは健全な壊れ方である」と言ったのはそのような理由からです。
ただし、誤解のないように言っておきますが、この「健全な壊れ方」というのは、あくまでも建物が徐々に水平剛性を失っていくプロセスを指すのであって、「部材が壊れる・破壊する」という話ではありません。個々の部材レベルにおいては、靭性破壊だろうと脆性破壊だろうと、壊れてはいけないのです。
なぜなら、壊れた後、その部材がどうなるのかよく分からないし、したがって責任が持てないからです。
ご存知のとおり、通常の構造計算で扱う部材の応力は「曲げモーメント」「せん断力」「軸力」の 3 つですが、増分解析法では、いずれの力についても、さきほどの図を単純化した下のような部材モデル(力と変形の関係)を使用します。注)
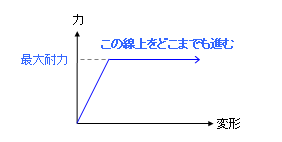
注)
これは、2 本の折れ線で構成される「バイリニア」と呼ばれる最も単純なモデルです。この他に、最大耐力に至る手前にもう一つの折れ点(通常はコンクリートのひび割れ耐力をあらわす)をもうけ、3 本の折れ線にした「トリリニア」と呼ばれるモデルを使うこともありますが、最大耐力に達した後の挙動は同じです。
つまり、「最大耐力に達するまでは弾性で、その後、その耐力を保持したままどこまでも変形についていく」と考えるのです。ここには「壊れる」という概念はありません(言うまでもなく、「壊れる・破壊する」とは、自分がそれまで保持していた耐力を丸ごと放棄する、ということです)。
が、しかし、実際に部材は壊れます。
そこでどうしたのかというと、「壊れずにどこまでも変形についていく」という前提を別の角度から担保することにした。それが「構造特性係数」なのです。
構造特性係数とは、「建物は保有水平耐力に達したが、しかし個々の部材は壊れていない」という状態を保証するものです。
そして、これは同時に、増分解析法による解析結果の正当性そのものを保証していることにもなります。
なぜなら、さきほども言ったとおり、もしどこかの部材がすでに壊れているのであれば、増分解析の結果そのものが「アテにならない」からです。
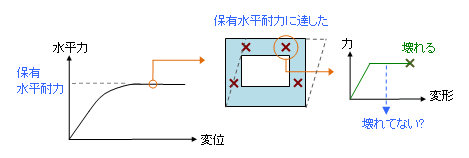
つまり、こうです。
もし、増分解析によって得られた保有水平耐力が(構造特性係数を勘案した)必要保有水平耐力を上回っているのであれば、部材が壊れている可能性は小さく、その解析結果は信頼できる。
逆に、必要保有水平耐力を下回っている場合は、どこかの部材が壊れている可能性が大きい。
増分解析法とは「部材が壊れていない」ことを前提とするものなので、その結果はアテにならない(だから条件を変えてもう一度やり直してください)。
先に述べたとおり、構造特性係数の算出根拠となるのは個々の部材の「ランク」ですが、変形能力が劣る、つまり「壊れやすい」部材ほど点数が低くなります。壊れやすい部材を壊れにくくするには「耐力」の方を上げるしかない。だから、壊れやすい(点数が低い)部材の集合に対しては構造特性係数が大きくなり、必要とされる保有水平耐力の水準(必要保有水平耐力)が上がる、というわけです。
ここから先の話、つまり、個々の部材の「壊れにくさ・壊れやすさ」をどのように数値的に評価してランク付けするのか、そしてそれをどのように積み上げて構造特性係数とするのか、ということになると、これはもう、私の手には負えません。
ただ一つ言えるのは、部材ランクとは、その部材のエネルギー吸収能力の絶対的な評価ではない、ということです。
だから、ここで、「ランク B の部材のエネルギー吸収能力とはどれくらいのものなのか?」などと聞いてみても始まりません。ランキングというものがすべてそうであるように、これは「 A よりは低いが C よりは高い」としかいいようのない「相対評価」なのです。そういう意味では、かなりバクゼンとしたものです。
しかしそれにしても、もう少し工学的な裏付けがほしい、と思われる方は、日本建築学会から出ている「建築耐震設計における保有耐力と変形性能」などをお読みになってください。
