武藤清の登場
「真島健三郎 vs. 佐野利器」を柔剛論争の第 1 ラウンドとすると、第 2 ラウンドは「真島健三郎 vs. 武藤清」になります。武藤清は佐野門下の若手研究者(その当時 20 代)です。注)
注)
武藤清は戦後(昭和 43 年)、日本最初の超高層建築である霞が関ビルの構造設計者として名をなし、文化勲章を受けることになりますが、これは鉄骨で造られた「柔構造」です。
これを柔派への「転向」と見るかどうかは意見の分かれるところですが、少なくとも、100 メートルを超えるような建造物を造るには、その当時の現実的な選択として「柔構造理論による鉄骨造」以外になかったことはたしかでしょう。
彼はまず、「家屋の耐震設計方針に就て」(昭和 4 年 11 月・建築雑誌)という論文で「剛派」の主張を展開しますが、ここで彼は「減衰」という機構 注) にとくに注目しています。
注)
減衰という現象は、「揺れている振り子は、外から何の力も加わらなければ、やがて静止する」という事実によって説明することができます。
この場合、振り子を静止させるのは主として「空気との間に生じる摩擦力」ですが、地震で揺れている建物にも同様の機構(ただしこの場合には、建物を構成する材料の分子間の摩擦や、エネルギーが建物の基礎面から地盤に放出されることが原因となる)が存在します。この機構により、揺れている建物はやがて静止するのです。
「地震動により鉄筋コンクリート構造物に亀裂が入って固有周期が増し、それによって共振が起きる」という真島の説に対し、「亀裂が入ることにより減衰の効果も増し、それが揺れを抑制するので、そんなに心配するほどのものではない」と武藤は主張します。
ただし、ここで急いで補足しておく必要がありますが、武藤がここで言ったのは、「たとえ亀裂が入ったとしても」という仮定の話であって、剛派の基本的な主張は「亀裂を入れてはならない = それくらい剛に造れ」というところにあります。
つまり、「たとえ亀裂が入ったとしても減衰があるから・・・」という考え方こそが前項で説明した「逃げ道」であり、剛派が依拠する「安心理論」を裏づけるものなのです。
この論文にはもう一つの論点があるのですが、それを理解するには若干の予備知識が必要になります。
地震波は「縦波(P波)」「横波(S波)」「表面波」の三つから構成されています。
このうち、速度が大きく、一番最初に地表に到達するのは「縦波」ですが、これはあまり大きな揺れをもたらすことはありません。したがって初期微動と呼ばれます。
私たちが「XX地震はどれくらいの大きさだった」と言うのは、その後にやってくる「横波」と「表面波」による揺れのことを指します。これを主要動と呼んでいます。
この主要動も減衰してそのうち地震がおさまるわけですが、一般に横波の方が早く減衰し、主要動の後半では表面波の影響が顕著にあらわれるようになります。これが、「周期の長い、ゆっくりとした揺れ」をもたらすのです。
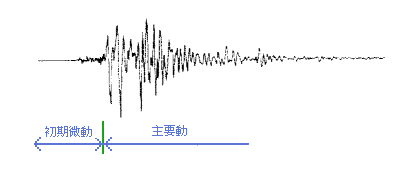
前置きが長くなりましたが、ようするに武藤が懸念しているのは、柔構造は、上に述べた「主要動の後半にあらわれる長周期の波」に共振するのではないか、ということです(実際、関東大地震でもその後半に周期が 2 から 3 秒くらいの波があらわれたとされている)。
しかも、柔構造の「ゆっくり揺れる」という性質のため、この共振が長時間にわたってつづく可能性がある。それに対し、剛構造は、たとえ共振を起こしたとしてもその時間はごく短いものになるであろう、というふうに武藤は剛構造の優位を説いています。
ただし、真島は建築学会の会員ではなかったこともあり、「建築雑誌」に掲載された上記の論文の存在は知らなかったようです(後の論争の過程で、「そのような論文を掲載したのであれば御一報願いたかった」と苦言を呈している)。
その間に真島はどうしていたかというと、昭和 5 年に「地震と建築」という本を出版(私は未見)し、さらにその内容を一般向けにした「耐震構造への疑ひ」という記事を昭和 6 年 2 月の東京朝日新聞(現在の朝日新聞の前身)に計 4 回にわたって連載しています。注)
注)
一般紙にこのような連載が載ることからも分かるように、その当時、柔剛論争はたんに建築界にとどまらず、一つの社会的なトピックとして扱われていたのです。またこの記事では、主として、その前年に起きた別の地震による被害の分析に基づいて柔派の主張を展開しているのですが、これについては次項で取り上げます。
これに対して武藤が「真島博士の柔構造論への疑い」(昭和 6 年 3 月・建築雑誌)を発表し、さらにそれを受けた真島が「柔構造論に対する武藤君の批評に答へ更に其の餘論を試み広く諸家の教を仰ぐ」(昭和 6 年 5 月・建築雑誌)という猛々しいタイトルで反論する、というのが柔剛論争の第 2 ラウンドでした。
論点の一つ一つを紹介するのは骨が折れるので止めておきますが、さきほど述べた、「柔構造では、主要動の後半に起きる長周期の地震動に共振する可能性がある」という武藤説に対しては、真島は「地震による被害の大半は主要動の初期にあらわれる短周期の波によるものである」と反論しています。
