エネルギーの分配
前回の内容を読みながら、あるいは、以下のような疑問を持たれたかもしれません。
地震のエネルギーの「総量」よりも建物全体が吸収できるエネルギーの「総量」の方が大きければよい、そして、建物全体が吸収できるエネルギーの総量は「各階」が吸収できるエネルギー量の総和である、と言っている。
しかし、「建物全体」のエネルギー吸収量が十分であったとしても、これを「各階」(建物の各部分)ごとに見ていけば、必ずしも十分とはいえないケースだってあるのではないか?
前回話したように、建物に関しては「各階」のエネルギーを足し合わせて「全体」のエネルギーをもとめています。この流儀を逆に使えば、地震のエネルギー Ed を各階に「分配」することだってできるはずです。ここで、各階に分配されたエネルギーを Edi という記号であらわすならば、作用する全エネルギー Ed は
Ed = ∑ Edi
のようにあらわされます。この Edi と各階の Wei を比較して検証する、というのが、間違いなく「本筋」のはずです。
しかし損傷限界の検証では、そのような手続きは踏まず、「全体として OK ならば、各階も OK なはず」と考えました。「なぜ、それでいいのか」というのが今回の話です。
建物に地震のエネルギーが作用すると、そのエネルギーが何らかの形で各階に「分配」されます。これは間違いありません。そしてその結果、各階に「層せん断力」が発生しますが、その時にどのような層せん断力が発生しているのかというと、それは「 Ai 分布にもとづく層せん断力」である、とエネルギー法は考えるのです。これは逆にいえば、
「各階に Ai 分布にもとづく層せん断力が発生している状態」を、「各階にエネルギーが適正に分配されている状態」とみなす
ということでもあります。
それがなぜなのか、というのは、種々のデータの蓄積から得られたものらしいので、ここで私が逐一説明することはできませんが、エネルギー法では、とにかくそういうふうに考えるのです。
そしてここでは、建物の損傷限界状態は Ai 分布にもとづく層せん断力によって定めること となっています。だからこの場合は、「全体」だけを見ておけば、わざわざ「各階」にまで下りてきて個別に検証するする必要はなかったのです。
ここに述べたのは、損傷限界、つまり建物が「弾性」状態にある場合の話ですが、弾性域を超えて「塑性」状態に入った場合でも、その基本的な考え方は変わりません。
下図にあるように、塑性域に入った後の各階のエネルギー吸収量の比が、弾性域における( Ai 分布にもとづく層せん断力が生じている時の)エネルギー吸収量の比と同じであれば、それをもって「エネルギーが適正に分配されている」と考えるのです。
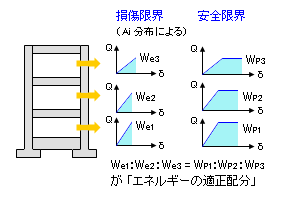
しかし、塑性域に入った場合(安全限界の検証)は、このようなエネルギーの適正な配分が必ずしも保証されるわけではありません。そこで、こちらについては、「エネルギーを各階に分配して各階ごとに検証する」という手続きがとられることになるのですが、話がだいぶ先走ってしまいました。安全限界についていうのなら、まず、「安全限界において建物に作用するエネルギー」の話から始めるべきでしょう。
