安全限界時に作用するエネルギー
安全限界時に作用するエネルギーも、当然ながら、運動エネルギーの基本式によりもとめます。M を建物の質量、Vs を換算速度値とすると、安全限界時に作用するエネルギー Es は

であらわされます。換算速度値 Vs は、安全限界時の固有周期 Ts から速度応答スペクトルを使ってもとめることになりますが、問題は Ts の算定方法です。
限界耐力計算では、この値を「建物の安全限界状態における等価剛性と変位」からもとめることになっていました。しかし安全限界状態の定義そのものがアイマイな上、この値をを大きくとればとるほど応答値が小さくなるという仕組みになっているため、ここには非常にデリケートな問題が含まれていました。一時期、「限界耐力計算は建設コスト削減のためのツールではないか」という声がしきりに上がったのはこのあたりの事情に関わるものです。
しかしエネルギー法では、少なくとも上のような事態は回避されています。なぜなら、Ts を定めるというよりは、安全限界時の換算速度値 Vs を直接定めるような形になっているからです。具体的には、下図にあるように、「速度応答スペクトル上で、損傷限界時の周期 Td を超えてある一定の範囲内にある最大の速度応答値を Vs とすること」と決められています。
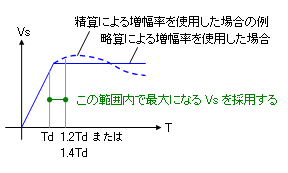
ここにいう「一定の範囲」とは、告示によれば、「鉄骨造で水平力を負担する筋かいのない剛節架構その他の地震による塑性変形を受けた後に剛性および耐力が低下しない復元力特性を有するもの」が 1.2Td、その他のもので 1.4Td としてよいことになっています。
上図を見ていただければ分かるように、表層地盤の増幅率を略算によってもとめている場合は、「固有周期が大きくなるにつれて Vs が大きくなる」と「固有周期の値にかかわらず Vs が一定になる」という二つの状態しかありませんから、一般に、1.2Td または 1.4Td をそのまま Ts として採用しておけばいいことになります。
以上の手続きにより、安全限界時に作用する地震のエネルギーがもとめられるのですが、しかしエネルギー法では、この値をそのまま安全限界時の検証に使うわけではありません。
下図にしたがって説明しますが、ここにあるように、地震のエネルギーによって建物の変形が弾性域を超え、O → A → B という経路をたどったとすると、この時に建物がなした仕事、つまり作用したエネルギーの総量は台形 OABD の面積に相当します。この台形は三角形 OAC と長方形 ABDC の二つに分解されますが、前者が建物の「弾性ひずみエネルギー」、後者が「塑性ひずみエネルギー」をあらわします。
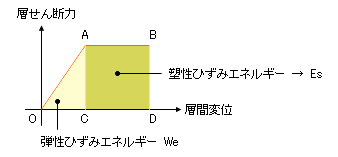
エネルギー法では、安全限界の検証対象として、もっぱら上記の「塑性ひずみエネルギー」だけをとり上げることにしています。そこで、作用する全エネルギーから弾性ひずみエネルギー We (多層の建物では、各階のエネルギー吸収量の総和 ∑Wei )に相当する分をあらかじめ「天引き」してしまい、これにあらためて Es という記号をあてることにすると、冒頭に掲げた式は
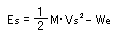
と書き換えられます。この Es が「安全限界時の必要エネルギー吸収量」です。注)
注)
さきほど「天引き」という言葉を使いましたが、じつは、ここにはもう一つ「天引き」されているものがあります。限界耐力計算(許容応力度計算・保有水平耐力計算も同じ)で使う加速度応答スペクトルは「減衰定数 0.05 」という条件で作られていましたが、エネルギー法で使う速度応答スペクトルも同様です。したがって、この Es の値には、「建物の減衰機構によるエネルギー吸収」の値があらかじめ「天引き」されていることになります。このあたりの事情は、損傷限界時の Ed についても同じです。
ところで、さきほど言った We (あるいは各階の Wei )とは「損傷限界状態に至るまでに建物が吸収したエネルギー量」で、損傷限界の検証を終えた時点で私たちはこの値を知ることになります。が、だとすると、さきほどの話といささかツジシマが合わない部分が出てくるのです。下の図を見てください。
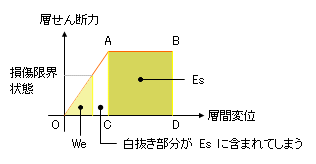
損傷限界とは、建物の弾塑性特性上の降伏限界(上図の A 点)を指すものではありません。これは、「どこかの部材の縁応力度が最初に短期許容応力度に達した時点」と定義されるものです。
したがって、建物の損傷限界状態は、この図の直線 OA 上の「A 点の手前のどこか」にあることになり、そこからもとめた We の値は三角形 OAC の面積よりも小さくなります。ということは、全エネルギーに相当する台形 OABD の面積から We を引くと、私たちが本来もとめようとしている長方形 ABDC の面積にはならず、この図の白抜き部分に相当する面積がくっついてくるのです。
これは、理論的には明らかに「おかしい」のですが、しかし、設計実務上の観点から見た場合は、「安全限界時必要エネルギー吸収量を実際よりも多めに見積もる」という安全側の評価になります。そういう理由から、「これでいい」ということになっているのです。
