基礎は浮き上るか?
これまでたびたび引き合いに出してきた技術基準解説書という本は 2007 年版ですが、その前身は 2001 年版で、さらにその前にさかのぼると「建築物の構造規定」「構造計算指針・同解説」というふうに書名が変わっていますが、2007 年版よりも前のものでは、いずれにおいても、「基礎の浮上り」に関して以下のような同じ文章が載っています。
中高層の共同住宅に供する建築物等のように短辺方向の長さの短い板状の建築物では、地震時の転倒モーメントによる浮き上りによって保有水平耐力が支配されることがある。
しかしながら、・・・
(途中略)
このため、建築物全体の浮き上りによる転倒が生じる可能性にある場合にあっても、浮き上がりが生じないものとして、それ以外の崩壊メカニズムの形成条件を考慮することができる。
途中の文章は長いので省略しました(内容についてはこれから説明します)が、この文章の流れは以下のようになっています。
- 二次設計において、机上の計算では「基礎の浮き上がり」によって建物が不安定になり、保有水平耐力が決定される場合がある。
- しかし、実際にそのようなメカニズムで建物が崩壊にいたることはない(ようである)。
- したがって、二次設計において「基礎の浮き上がり」は考えなくてもよい。
このような結論にいたった理由が、先の引用の「途中略」にあるのですが、それを要約すると下のようになります。
- Ai から得られる地震力の分布をもとにして計算された建物の転倒モーメントは実状に比して過剰な値を与える。したがって、その値をもとに「基礎が浮き上がる」という結論にいたったとしても、一概には信用できない。
- 基礎の浮き上がりによって建物が転倒にいたるメカニズムは、少なくとも、現在考えられているものよりはずっと複雑であろう。
- 地盤そのものを原因とするもの(液状化等)を除き、実際に大地震で建物が転倒したという事例はほとんど知られていない。
後の二つについては私は分からないので、ここでは最初のものについて説明します。
が、そのためには、「設計地震力とは何なのか?」の話から始めないといけないので、少々遠回りさせてもらいます。
増分解析法は別名「静的弾塑性解析」とも呼ばれます。同様の表現を使えば、一次設計における応力計算は「静的弾性解析」です。
この「静的」とは何かというと、ここには「時間」という要素がない、それを切り捨てている、ということです。これに対し、建物モデルの基礎部分に地震波を作用させて時系列の性状を追跡するのが「動的解析」(あるいは「時刻歴応答解析」)です。
動的解析の場合は、刻々と地震力が変わることそのものを追跡するわけですから、どのような外力分布をもちいるか、という問題は生じません(そのかわりに「どのような地震波をもちいるか」が問題になりますが)。
以前に、Ai 分布とはどんなものかを説明した時に、技術基準解説書の一部(P.306)を引用しましたが、こんな内容でした。
建築物が弾性域にある状態及び部分的又は全体的に塑性域に入って崩壊に近いほどの大きな変形に達した状態等における外力分布については数多くの地震応答結果が蓄積されており、それをまとめたものが Ai 分布にもとづく外力分布である。
ここにある「数多くの地震応答結果が蓄積されており・・・」というのが、じつは、この動的解析によるデータの蓄積を指しています。具体的にどうしたのかというと、
多くのサンプル建物の動的解析結果から、それらの各階に作用する地震力の最大値を抽出し、それを簡便な式にまとめて Ai とした
のですが、ここで大事なのは「各階の力が同時に最大値に達するわけではない」ということです。
簡単な 2 階建ての建物を例にとって説明します。
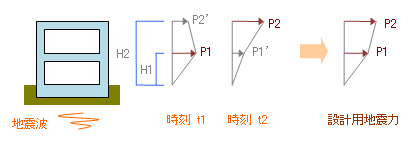
時刻 t1 において 2 階床に最大の地震力 P1 が作用することが動的解析により分かりました。
さらに、もう少し後の時刻 t2 において 3 階床に最大の地震力 P2 が作用することが分かりました(こういうふうに最大値の発生時刻がずれるのは「高次モードの影響」として説明されるのですが、詳しい内容については省略します)。
で、この事実を受けて、設計用の地震力を P1 と P2 に決めるのですが、実際には、2 階床に P1 が作用している時は 3 階床に作用している地震力は P2 よりも小さく、3 階床に P2 が作用している時は 2 階床に作用している地震力は P1 よりも小さいのです。
ここから、以下のように言うことができます。
設計用の地震力の分布とは、設計上の便宜のためにしつらえたものであり、地震力を受けている建物のある瞬間をスナップショットにように切り取ったものではない
なぜこんなことをわざわざ言うのかというと、つい私たちは、一次設計なり二次設計なりの「地震荷重時応力図」を眺めながら、「実際に地震がくると建物にこういう応力が起きるのだな」と勘違いしてしまうからです。
まあ、べつに勘違いしたところで、「その応力に対して部材をデザインしなければならない」ことに変わりはないし、それによって建物の安全性が保証されるわけですから、それはそれでいいのですが、ここで話題にしている「基礎の浮き上り」のような現象を考える場合には、このことが問題にされます。
というわけで、「基礎の浮き上がり」に戻ります。
建物を基礎面で固定された「片持ち梁」と考えると、作用している地震力はこの梁に作用する中間荷重ということになりますので、その結果、建物の基礎面(固定端)に曲げモーメントが生じます。これが「転倒モーメント」です。
この曲げモーメントをアームの長さで割ったものが「引き抜き力」(もう片方は「押し込み力」)で、これが基礎に下向きに作用している鉛直方向の荷重(常時荷重)よりも大きくなると「基礎が浮き上がる」というふうに考えるのが通常の設計です(これに対し、上に掲げた二番目の理由では、「そんなに単純な機構ではないのではないか」と言っているわけですが)。
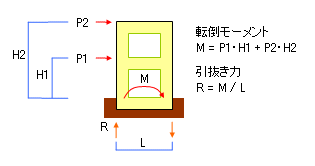
当然ながら、この時の地震力とは Ai 分布から得られたものを使うわけですが、先に述べたとおり、この設計用地震力は、「ある時刻において建物に実際に作用している地震力」ではありません。「一定時間内に建物の各階に生じるであろう地震力の最大値を縦に並べたもの」です。
だから何が問題なのか、というのは、冒頭の図に戻っていただければ容易に理解できるはずです。
設計地震力、つまり「各階の最大値が同時に作用した」と仮定した時の転倒モーメント M ( 図の記号であらわせば P1・H1 + P2・H2 )は、「地震時にこの建物に作用すると考えられる転倒モーメントの極限の値、絶対にこれ以上にはならないと保証できる最大の値」ではあっても、「実際に生じるであろう最大の値」とはいえません。実際に生じる最大の値は、時刻 t1, t2, ・・・ において生じている値のうちの「どれか」なのです。
ここから、設計地震力から得られた転倒モーメントの値は実状よりも必ず「過剰」になり、そしてその「過剰」の度合いは高層の建物ほど大きくなるはず、という結論がえられます。注)
注)
日本建築センター「高層建築耐震計算指針」では、基礎の浮き上がりの検証に使用するための「転倒モーメントの低減係数」が提唱されています。これによれば、建物の階数が多いほど転倒モーメントを小さく見積もることができるようになっているのですが、その理由はここに述べたとおりです。
もちろん、ここに述べた「過剰な転倒モーメント」という問題は、何も二次設計に限ったことではなく、一次設計においても事情は同じですが、「ではどうしたらいいのか」ということになると、大変困ります。
日本建築学会「地震荷重 - その現状と将来の展望」という本 ( P.269 ) では、「(転倒モーメントと基礎の浮き上がりに関する)現状のクライテリア」として、以下のような提案がなされています。
- 中地震時の転倒モーメントに対しては基礎に浮き上がりを生じさせない。
- 大地震時の転倒モーメントに対しては過大な浮き上がりを発生させない。
当然、この「過大な浮き上がり」とはどういうものなのか、が問題になります(この本では「今後の課題」とされている)が、私が見聞きしている範囲では、
一次設計(中地震時)において基礎の浮き上がりがないように設計しておけば、大地震時に建物の転倒が生じるようなことはないと考えられる(あるいは、そのように考えてもよい)。
だから、二次設計(大地震時)で基礎の浮き上がりを考慮する必要はない。
というのが、今のところの常識的な考え方なのではないかと思います。
ただし、最新版である 2007 版の技術基準解説書では、塔状建築物(塔状比が 4 を超える)に対しては基礎の浮き上がりを考慮することをもとめているので注意が必要です。ようするに、こういう建物は一般に転倒に対する安全率が低いから、という理由なのでしょうが、以下に、その部分を引いておきます ( P.310 )。
