どれぐらい安全か?
これまでの話をまとめてみると、
- 想定した限界状態において「耐力」と「荷重効果」を比較し、前者の方が大きければ「安全」とすることができる。
- しかし耐力にしても荷重効果にしても、それを「確定値」とすることはできない。多くの場合、これらは正規分布もしくはこれに近い確率分布曲線として表現される。
ということになりますが、ここで耐力の確率分布を R、荷重効果の確率分布を S として下図のように描いてみます。
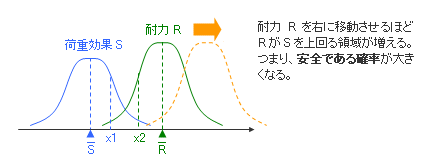
まず最初に、この図上で、現在行われている「許容応力度設計法」とは何なのかを考えるてみることにします。
私たちは、政令に定める荷重によって部材に生じる「応力」を算定します。これが図の x1 の線ですが、ここには何がしかの安全率が含まれているので、おそらく S の平均値よりも右側にあるでしょう。
次に私たちは、これも政令その他に定めた「許容応力度」の値をもとに部材の「許容耐力」を算定します。
当然ながら、ここにも安全率が含まれていて実際よりも値を小さく見積もっていますから、その値を表す x2 の線は R の平均値よりも左側に位置するはずです。
これらの値を「確定値」とし、x1 よりも x2 の方が大きければ安全である、と考えるのが「許容応力度設計法」です。
しかしこれまで学んできたところによると、本当の荷重効果(応力)は確率分布を表わす青い線上のどこかにある(どこにあるかは分からない)はずだし、本当の耐力も確率分布を表わす緑の線上のどこかにある(どこにあるかは分からない)のです。だから、「 X2 が X1 よりも大きい」という事実をもって「安全」とすることは必ずしもできないはず−−ようするに、これが「限界状態設計法」の言い分です。
かと言って、許容応力度設計法の側もそのような事実を知らないわけではありません。なぜなら、(その根拠があまり明確でないとはいえ)そのような不確定性を安全率に換算して「許容応力度」という値を定めたはずなのですから。
しかし場合によっては、対象としている事象の不確定性が強く、既定の安全率では安心できないようなケースも出てきます。そのような場合によく使われるのが「応力の割増率」という考え方です。
この仕組みをさきほどの図にしたがって解読してみます。
「応力を割り増す」ということは、実際に算定された応力を表わす x1 の線を何がしか右に移動させる−−確率分布を表わす青い線そのものを移動させるのではない−−ことを意味しています。そして、この割り増された値をもとにした断面設計を要求されると、設計者はさきほどよりも耐力を何がしか「増やさざるを得なくなる」ので、耐力の分布を表わす緑色の線も(オレンジ色の破線のように)自然に右に移動するはずです。
その結果、荷重効果 S を表わす青色の線と耐力 R を表わす緑色の線の「間隔」がさきほどよりも大きくなる。この間隔が大きい、ということは「 R が S を上回る領域が大きくなる」ことを意味します。つまり、それだけ「安全である確率が大きくなる」のです。
限界状態設計法は、上のような手続きを、より分かりやすく、かつ定量的に表わすことを目指したものだと言えるでしょう。
安全である確率は「 R > S となる領域」の面積に相当しますが、まず、この右辺を移項して「 R - S > 0 となる領域」と読み替えます。これに M という名前の新しい確率分布を与えると、
M = R - S > 0 であれば、安全
と言えることになる。幸いなことに、R も S も正規分布するとすれば、両者を加算・減算したものも正規分布することが分かっています。
したがって、この M は下図にように描くことができ、M < 0 となる部分の面積が「安全でない」とされる確率(破壊確率)を表わすことになります。
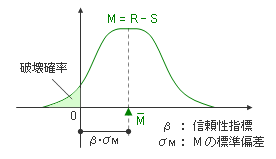
もちろん、この時に「安全である確率」は「 1 - 破壊確率」です。しかし一般には、これをもう少し分かりやすい表現に改めます。
上図にあるように、原点から M の平均値(山の頂き)までの距離を M の標準偏差σM で割ると、この距離が標準偏差の何個分に相当するかが分かります。これは信頼性指標と呼ばれる値で、通常βという記号で表わされます。
このような表現をとることの有意性については先に述べました。
ある値が母集団内で「ふつうのもの」なのか「特異なもの」なのかの目安を得る最も分かりやすい方法は、「その値から平均値までの距離が標準偏差の何個分に相当するか」を見ることなのです。
下図左にβが 0 の時の M の分布を示しました。当然、この場合の破壊確率は 0.5 になりますから、こういう「のるかそるか」みたいな設計はご法度です。
右にあるのがβを 1 とした時の図ですが、この時の原点から平均値までの距離は標準偏差に等しくなります。これも前に述べた通り、平均値から標準偏差 1 個分離れた領域というのは「ごくふつうに存在するデータのバラつき」と見なさなければなりませんから、ここから、
信頼性指標βは少なくとも 1 以上にしておく必要がある
ということが分かります。
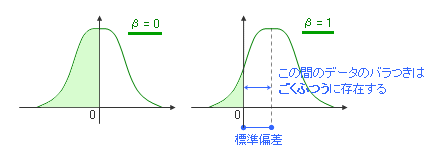
βが 1 の時の破壊確率がどれくらいになるかは簡単に分かります。
全体の約 70% が「平均値 ± 標準偏差」の中に含まれるのですから、「平均値 - 標準偏差」の中にあるのはその半分の 35% です。したがって、その範囲から外れるものの割合は(平均値から左側にある半分だけを考えると) 0.5 - 0.35 = 0.15 ということになり、これがβを 1 とした時の破壊確率です。
ちなみに、βを 2 にすると破壊確率は約 0.02 と急速に小さくなり、3 にすると 0.001 強くらいの値にまで減少します(実際の設計においては、一般に、βの値として 1 から 2.5 くらいの値がとられる)。
さて、この項で得た知識から以下のようなことが分かりました。
何らかの形で「許容できる破壊確率」を定めれば、そこから「目標とすべき信頼性指標」が得られる。それを照準として設計を進めていけば、結果として、建物の安全性を定量的に表わすことができる(はず)。
つまり、これが「信頼性設計法」(あるいはその理念を取り入れた「限界状態設計法」)というものなのです。
