荷重もバラつく
前項では、「耐力のバラつき」をもたらす一つの例として「コンクリート強度のバラつき」を取り上げ、この値が正規分布するものであることを話しました。ではそもそも、どういうものが「正規分布する」と見なされるのでしょうか?
これはようするに、
ある事象に関するデータ群の平均値というものが何らかの意味を持ち、それがそのデータ群の典型的な値をあらわすもの
と考えておけばいいのではないかと思います。
じつは、構造設計に関わるほとんどのデータは正規分布あるいはそのバリエーション(ここではふれないが、データの値の自然対数が正規分布する「対数正規分布」というものもある)に含まれると考えられています。
たとえば、「鋼材の強度」というものを取り上げてみます。
現在の規定では、保有水平耐力の計算時に規格値の降伏強度を 1.1 倍してよいことになっていますが、これは、実際の降伏強度が規格に定める下限値よりも 1.1 から 1.2 倍ほど大きくなっているという統計データに基づくものです。
したがって、コンクリートほどのバラつきはないものの、鋼材の降伏強度もその辺の値(規格値の 1.1 倍くらい)を「山」とし、その両側に「裾野」を持って正規分布していると考えていいでしょう。
耐力のバラつきを左右する要因は材料の強度だけではありません。
鉄骨でいえば形鋼の寸法誤差というものもあるし、コンクリート構造物でいえば型枠寸法の施工誤差があります。さらに、耐力算定式の精度による誤差(実際の耐力は机上で計算されたものより大きかったり小さかったりする)もありますが、いずれにしても、これらは正規分布するものと考えてほぼ間違いなさそうです。
では、その「耐力」の比較対象である「荷重」の方はどうでしょうか?
固定荷重についてはほとんど「確定値」としてもいいかもしれませんが、もろもろの要因を考慮して「変動係数の小さな正規分布」とすることができそうです。
積載荷重については、その対象とする面積が小さければ大きく変動します−−例えば 1m 四方の床を考えると、その上を人が通り過ぎるたびに荷重が大きく変動する−−が、対象面積を大きくするにつれて変動係数が小さくなり、正規分布に近づくものと考えられています。
その一方、荷重の中には、とても正規分布するとは思えないものもあります。
その典型的な例が「地震」です。
地震の大きさを横軸にとり、その発生度数を縦軸にとってグラフを描いてみると、下図にあるように、「規模の小さな地震は頻繁に起き、大きくなるにつれて発生頻度が急激に減少する」ような形になることは容易に想像できるでしょう。
この値の「平均」をとってみても何の意味もありません。地震の大きさに「典型的な値」は存在しないのです。注)
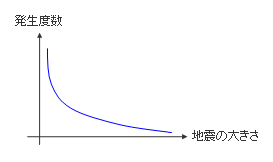
注)
マーク・ブキャナン著「歴史は『べき乗則』で動く」(ハヤカワ文庫NF)という本によると、地震のマグニチュードが 2 倍になるとその発生頻度は 1/4、3 倍になると 1/9 になるとされています。
このように、二つの変数 x と y が y = c・x n という関係( c と n は定数、この場合は n = -2 )になる時、x と y は「べき乗則」にしたがう、と言います。この本には他にもいろいろな例が紹介されていて、なかなか興味深い。
このあたりの事情は「雪」あるいは「風」のようなものについても同様ですが、このような荷重に対してとられる考え方が、
ある一定期間内に生ずると予測される「最大値」を確率的に求め、それを設計荷重とする
という考え方です。確率・統計の用語では、上の「ある一定期間」を再現期間、「予測される最大値」を再現期待値と呼びます。
これの最も身近な例は、現行法規に定める雪の「垂直積雪量」や風の「標準風速」です。たとえば、平成 12 年建設省告示第 1455 号第 2 に以下のような文章があります。
当該地域又はその近傍の区域の気象観測地点における地上積雪深の観測資料に基づき統計処理を行う等の方法によって当該区域における 50 年再現期待値(年超過確率が 2 パーセントに相当する値をいう)を求めることができる場合には、当該手法によることができる。
この「 50 年再現期待値」とは、「 50 年というタイムスパンの中で遭遇するかもしれない最大値」のことです。
これは言葉を換えると、「 1 年」を基本単位とした時に「 50 回続けてクジを引けば 1 回は当たるであろう」ということですから、次の 1 回( 1 年)で当たる確率は 1/50 になります。上の文章にある「年超過確率が 2 パーセント」とはそういう意味です。注)
注)
ちなみに、「当たらない」確率の方は「非超過確率」と呼ばれます。これは「 1 - 超過確率」になりますから、上の例で言えば、「その 1 年で最大値を上回らない確率」は 98 パーセント( 0.98 )ということになります。
これをたとえると、100 回のうち 98 回は表が出るように細工された「いびつなコイン」を使ってコイン投げをしているようなものと言えます。次の 1 回で表が出る確率は 0.98 ですので、これを 50 回投げた時にすべて表が出る( = 50 年にわたって最大値を上回らない)確率は 0.98 を 50 回かけた 0.9850 = 0.36 という数値で表わされます。
逆に、1 回でも裏が出る( = 50 年の間のある年に最大値を上回る)確率は 1 - 0.9850 = 0.64 です。
ところで、現行の許容応力度設計法では「最大積雪量」という値がまるで「確定値」のように提示されているため、私たちはつい勘違いしてしまいがちですが、これは「過去に観測された記録の最大値」という意味ではありません。上の告示にあるように、「過去の観測資料に基づいて統計処理を行う」ことによって得られた「確率的な値」なのです。注)
注)
ただし、設計に使用する最深積雪量は基本的に各地方の特定行政庁が決めることになっていますから、地方によっては、これを「過去何十年かに記録された積雪量の最大値」としている所もあるかもしれません。
「雪が降る」という自然現象は「気候現象」というカテゴリーに入るものですが、これは間違いなく「 1 年」をサイクルとして繰り返されます(この場合は「一冬」と言った方がいいのかもしれませんが)。したがって、「ある 1 年の間に生じた最大値」というものを考えることはきわめて合理的と言えるでしょう。
そこで、過去に記録された「年間の最大積雪量」を横軸に表わし、縦軸にその度数(ある範囲の最大積雪量が記録された年の数)を表わしてみると、その形状は、下図にあるような「真中あたりに山があって両側に裾野が広がる」というものになります。
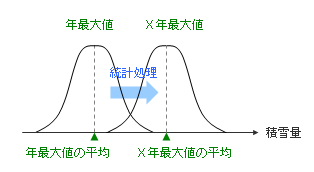
そしてこの時、このグラフの形状がある一定のルールに従うのであれば、そこから、ある再現期間内に生じると考えられる最大値、つまり「再現期待値」を統計的に推測することができるのです。これは極値分布という考え方に基づく統計理論なのですが、しかし、その内容をここで説明しろと言われても私にはできません(どんなものなのか大雑把でもいいから知りたい、と思う方は「ウィキペディア」でもご覧ください)。
そういうわけで結論だけを手短に書かせてもらいますが、X 年間における最大積雪量の確率分布は、上図右に示すように、もとの「年最大値」のグラフをそのまま右方向に移動したような形になるのです。
もちろん、再現期間を長くとればとるほどこのグラフは右に移動する(積雪量が大きくなる)ことになりますから、再現期間をどのようにとるかということが問題になりますが、現行法規でこれを 50 年としているのは、建物の一般的な耐用年数をとったものとされています。
ここまで述べたのは積雪荷重を定めるための基準値となる「積雪量」の話ですが、風荷重を定めるための基準値となる「風速」も、大筋においてはこれと同様です。
問題は「地震」です。これは雪や風とは違い、「 1 年をサイクルとして変動する気候現象」とは言い難いものがあります。
つまり、「 1 年間にその場所で起きた地震の最大値」を集計してみてもあまり信頼性のある統計量にはならないと考えられます。そこで、(現行規定の設計地震力に見るように)何らかの「経験値」に頼らざるを得なくなる 注) のですが、そのあたりの確率論に基づいた考え方については日本建築学会「建築物荷重指針・同解説」などを見て頂くことにし、「限界状態設計法」の話を先に進めます。
