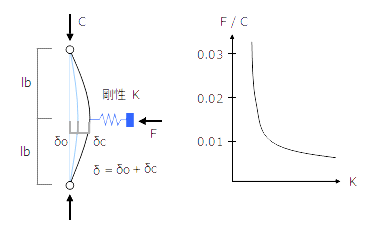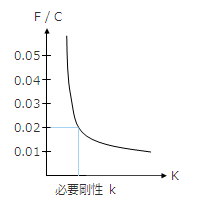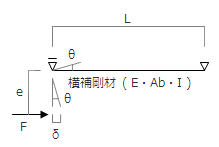|
横補剛材の必要剛性とは何なのか?
建築構造の行政審査は、すべてが法令に基づいて行われるわけではない。その他に、さまざまな「設計慣習」に基づいたチェックが行われる。この慣習は、建築学会の規準とか、いわゆる「黄色本」というような形で明文化されている場合もあるが、中にはまったくの「暗黙の了解」もある。
たとえば、「コンクリート系の建物の場合は風荷重の検討を省略できる」という慣習がある。建築基準法によれば、どんな建物であれ風に対する検討は行わなければならないことになっているのだから、それを怠ることは法令違反にあたる。しかし、審査側からそのような指摘を受けた、という話は聞いたことがない。同様の例は他にもあるだろう。
それはそれで構わないと思うのだが、しかし慣習というのは「いつの間にかそうなっている」ものなので、事情を知らない人にとっては「寝耳に水」ということもある。
ここで取り上げる「横補剛材の剛性のチェック」というのもその一つで、その検討を求める審査機関が増加しているようだ ( 実際、何年か前からそのような問い合わせが小社のプログラムサポートに多く寄せられるようになり、途中でプログラムを改定した経緯がある )。
そのきっかけとなったのは、(財)日本建築センター発行の機関誌「ビルディング・レター」( 2010 年 8 月号 ) の中にある「【質問と回答】横補剛材の強度と剛性の具体的な検討方法について」という記事 ( 以下、「質問と回答」と略記 ) らしい。
このような記事をこの時期に掲載することになった経緯はよく知らないが、とにかく、国の機関 ( に準ずるもの ) が発行する雑誌に載った記事であれば、それなりの影響力を及ぼすのは自然の成り行きかもしれない。
今後、これがそのまま「設計慣習」として定着していくのかどうかについては何とも言えない。が、それにしても困ったのは、ここに書かれている内容が私にはよく理解できなかったことである。
この記事の前段によれば、ここで行おうとしていることの主旨は、「主材の座屈荷重の 2% の力が横補剛材に作用した時、それに十分耐えられるだけの剛性を横補剛材に与えなさい」である。そして最後に以下のような図と検討式が載っている。
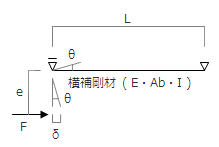
|
剛性の検討
K = F / δ ≧ 5.0 σy・A / ( 2 lb )
ここで δ = θ・e + F・L / ( E・Ab )
θ = M・L / ( 3 E・I ) = F・e・L / ( 3 E・I )
補剛材の剛性
K = 3 E・Ab・I / L / ( Ae・e2 + 3 I ) ≧ 5.0 σy A / ( 2 lb )
記号
K : 補剛材の必要剛性
θ : 補剛材の回転角
δ : 大梁の横たわみ
σy : 大梁の降伏点強度
A : 大梁の全断面積
Ab : 横補剛材の全断面積
lb : 横補剛区間長さ(補剛間隔)
|
これが雑誌の記事の一部であることを考えると、アラ探しのようなことは慎むべきかもしれないが、それにしても、この式を目にして私が最初に思ったのは「何だかよく分からない」だった。
まず、記号の説明で K を「補剛材の必要剛性」としているが、これは「補剛材の剛性」とすべきかと思う。
この値は「剛性の検討」と「補剛材の剛性」の表題の下に二度登場しているが、これは明らかに同じもので、表現を変えたに過ぎない。「補剛材の必要剛性」は、これらの式の不等号の右側にある値 ( 5.0 σy ・・・ ) ということになる。
この補剛材には大梁の側から ( 横座屈に伴う ) F という力が作用している。したがって補剛材の剛性は、これによって δ という軸方向の変形量が生じたとすれば F / δ になる。
ただし F が補剛材の軸心から e だけ離れて作用している場合、補剛材は F によって「縮む」だけでなく、F・e という曲げモーメントによって「回転」してしまう。その回転変形角が θ である。
軸力と歪み量、及び曲げモーメントと回転角の関係ならば構造力学の公式にある。そして最終的には、これらのの変形量を加算したものが δ になる。
――と、ここまでは何とか理解できるのだが、よく分からないのは「必要剛性」である。
どうやら、これについては、日本建築学会から出されている各種の設計指針 ( 鋼構造設計規準・鋼構造塑性設計指針・鋼構造座屈設計指針 ) にあたるしかないようである。そんなわけで、以下、これらの本から私が即席で仕込んだ知識を披露することにした ( 知っておけば何かの足しになるかもしれません )。
当初、私はこの「必要剛性」の式の意味を、
大梁が横座屈を起こすと横方向に F という力が発生するが、この力の大きさは大梁に生じている圧縮力の 2% に相当する。だからその力に対し、補剛材が過大な変形を起こさないように一定の剛性を与えなければならない。それが「必要剛性」である。
というふうに漠然と理解していた。しかし、どうやら違うらしい。
座屈によって材の直交方向に生じる補剛力 ( 本によっては「横力」となっている ) F と、それを受ける補剛材の剛性 K の間には一定の関係があり、剛性 K が大きくなるほど補剛力 F は小さくなる。つまり 補剛材の剛性が補剛力の大きさを決定する のだ。
下図左は、座屈荷重 C を受けている材の中央部に剛性 K の補剛材 ( に相当するバネ ) があり、この時、バネに反力 F が生じている状態をあらわしたものである。そして右のグラフでは、縦軸に F / C ( 座屈荷重に対する補剛力の比 )、横軸に補剛材の剛性 K をとって両者の関係を表わしている。
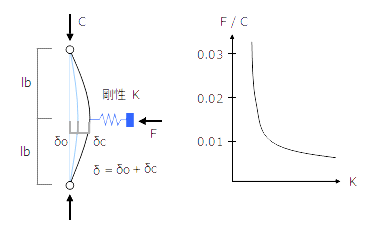
剛性 K が無限大であれば「完全拘束」という状態になるが、このグラフを見ると、K がある値を超えると F / C が一定値になり、その状態に向けて収束することが分かる。逆に剛性 K がある値以下になると F / C が急激に増大するが、これは「簡単に座屈してしまう」ことを教えている。
だからようするに、両者の境目になるところに「必要剛性」、つまり剛性の下限値を定めておけばいいわけだ。
ところで、座屈という現象は材の「元たわみ」、つまり部材を建て込んだ時に不可避的に存在するたわみを原因として起きるものと考えられている。したがって、上図にある補剛位置の変位量 δ は、力 F による変位量 δc と元たわみ量 δo の総和になるはずである。そして ( K に δ を掛けたものが F なのだから ) 元たわみ量が大きいほどこのグラフは上方に移動する。つまり、元たわみが大きいほど座屈しやすい、ということになる。
となると、事前に何らかの「元たわみ量」を仮定しないと話が始まらないわけだが、もちろん、本当の値は現場で計測しなければ分からない。しかし、それでは設計にならない。
そこで設計上の目安として「鉄骨の許容製作誤差」――たしか JASS に定められているはず――という値を使うことにした。この値は部材長に対する比で表わされ、1/500 とされているのだが、ここではさらに安全率を見込んで 1/250 という値を採用した ( このあたりは「そういうものなのだ」と了解しておくしかない )。
上図でいえば、これは δo / lb = 1/250 ということになるわけだが、この条件を入れると、ほぼ下のようなグラフが出来上がることになる。
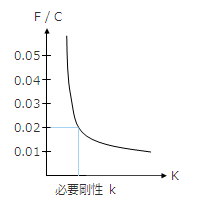
結局、上のグラフから補剛材の必要剛性 k を定め、これに対応する F / C の値を 0.02 ( F = 0.02 C ) ということにしたのだった。
ところで、剛性 K は F / δ だが、F を圧縮力 C に対する比、δ を補剛間隔 lb に対する比で表わすと、この値は C と lb の関数になる。下にあるのが「鋼構造塑性設計指針」で提案されている必要剛性 k の式である ( ここにある係数 5.0 は複数の研究成果を踏まえて総合的に判断されたもの )。
k ≧ 5.0 C / lb
次に C の値 ( 横座屈材に生じている圧縮力 ) だが、ここでは大梁を対象にしているので、「作用曲げモーメントによって生じている圧縮応力の合力」になる。設計曲げモーメントを断面係数で割った値とすることもできるし、あるいは弾性限界状態を考えて「フランジ断面積×降伏点強度」とすることもできるだろう。
ただし前記の「質問と回答」では ( 安全側の措置として ) 全断面が塑性化した状態を考えることを提案している。したがってこの場合、全断面の半分が圧縮降伏状態になるので、C の値は以下のようなる。
C = σy・A / 2
これをさきほどの必要剛性 k の式に代入すると、「質問と回答」にあった以下の「必要剛性」が得られることになる。
5.0 σy A / ( 2 lb )
( 文責 : 野家牧雄 )
|