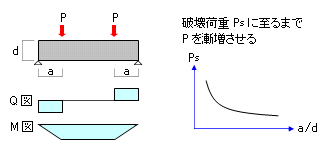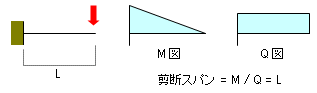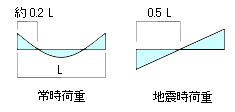|
M/Qd とは何なのか?
鉄筋コンクリート断面の剪断耐力を求める式の中に α という割増率があり、それが M/Qd ――「エムバーキューディー」と読む習慣がある――という値をパラメータにしていることはご存知かと思う。
ここにある d は「部材の有効せい」で、これについては異論の余地がない。しかし、 M ( 曲げモーメント ) と Q ( 剪断力 ) については、「一体どこの応力」なのか、ということがしばしば問題にされる。これについては必ずしも定まった考え方があるわけではなく、いわゆる「認定プログラム」と呼ばれるものの中でも仕様が若干異なっている。
小社製の断面計算プログラム「RCチャート」では、長い間これを「左右端の各部位における応力」としていたのだが、この点に関して、しばしば
学会規準ではこれらの値を「部材に生じている最大曲げモーメント、及び最大剪断力」としているのだから、部位ごとに考えるのはおかしくないか ( あるいは、役所から「おかしい」と指摘された )
という問い合わせがきていた。
そこで調べてみると、現在では、やはりそのような考え方をとるのが主流になっているようだった。そんなこともあり、現行版のプログラムでは「一般慣習」にしたがって仕様を変更することにしたのだが、しかしさらによく調べてみると、これはどうやら、「どちらが正しい・間違っている」というような問題ではなさそうである。
ようするに、これはよく分からないものではないのか、ということが分かってきた。
というわけで、今回はこの話題を取り上げることにする。
そもそも、この「剪断耐力を割増してもよい」という考え方は複数の実験結果をもとに得られた知見で、何らかの明快なメカニズムに基づいて説明できるものではない ( おそらく、そのメカニズムについてはよく分かっていない ) 。
で、その実験とはどんなものかというと、下図にある通り。
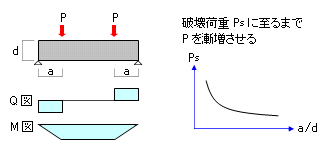
これは鉄筋コンクリートの試験体の二箇所に支点を設け、支点から一定の距離 a だけ離れた点に集中荷重 P を作用させるものである。ここで荷重 P をどんどん増やしていくと試験体はどこかで「壊れる」が、この時、多量の引張鉄筋を入れる等の方法で実験体の曲げ破壊を防止しておく。したがって、試験体が破壊した時の荷重の大きさを Ps とすれば、これを試験体の「剪断耐力」を表わしていると考えていいことになる。
ところで、ここにある「Q図」に見るように、支点から a の範囲内の剪断力 Q はつねに一定 ( = P ) で、a の値には依存しない。だから、理屈の上では a の値をいくら変えても耐力 Ps は変わらないはずだが、しかし実際にやってみると、これが変わってしまった ( しかも大幅に ) 。
具体的にいうと、a の値が小さいほど耐力 Ps が大きくなったのである。
さらにもう一つ分かったのは、「 a の値が同じなら部材のせい d が大きいほど耐力が上がる」ということ。そこで横軸に a/d、縦軸に耐力 Ps をとってグラフに表わすと、上図の右にあるような左上がりの曲線が描かれることになった。この a を剪断スパン、a/d を剪断スパン比と呼んでいるが、ようするに
剪断スパン比が小さいほど剪断耐力が上がる
わけで、これが私たちが使っている「割増率 α 」のもともとの考え方になる。
ところで、さきほどの図を見ていただければ分かるように、ここにある「剪断スパン a 」の値は、本来は「剪断力が一定であるような区間の長さ」を指すものである。しかし実験ならばいざ知らず、複雑な応力が生じている実際の部材にこの考え方をそのまま適用するのは明らかに無理がある。そこで、実務設計ではこれを「部材の端部から曲げモーメントが 0 になるような位置までの距離」というふうに読み替えることにした。
その最も分かりやすい例は、下図左にあるような「先端に荷重が作用する片持ち梁」である。
この場合は部材の長さがそのまま剪断スパン ( = Q が一定になる区間 ) に相当し、これが M/Q という値で表わされることが分かる。
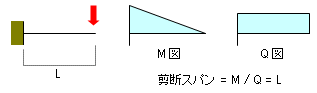
ここから、
M/Q という値で「部材の端部から曲げモーメントが 0 になるような位置までの距離」を表わし、それを「剪断スパン」に相当するものと考える
ことにしたのである。
この考え方にどれくらいの妥当性があるかということを、たとえば下図左にあるような「等分布荷重を受ける両端固定梁」について計算してみる。
部材長を L としとた場合、「曲げモーメントが 0 になるような位置までの距離」は 0.22L で、一方の M/Q の値は 0.17L だから、これを四捨五入して「約 0.2L」とすれば「ほぼ合っている」と考えていいのかもしれない ( 見方にもよるが ) 。
さらに下図右にあるような地震時の応力状態であれば、こちらは 0.5L でぴったり合う ( この図とさきほどの図を見比べれば分かるように、これはつまり、部材の端部を取り出し、それを「曲げモーメントが 0 になるような位置」に集中荷重が作用している片持ち梁に見立てていることに相当する ) 。
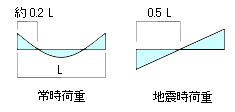
実際の設計では、上の二つを足し合わせたものを使って短期荷重時の設計をすることになるので、この場合は 0.2L と 0.5L の中間ぐらいになると考えていいだろう。
しかしそれにしても、実際の部材の応力状態はもっと複雑である。そんなこんなを考え合わせれば、これはどこまで行っても「大体こんなもの」という値にしかならないのではないか。そもそも、「どんな応力状態においても M/Q を剪断スパンと見なしていいのか」という点についても疑問がないわけではないだろう。
冒頭で、M と Q をどのようにとったとしても、「どちらが正しい・間違っている」と一概にいうことはできないのではないか、と書いたのは実にそういう意味なのでした。
(文責 : 野家牧雄)
|