柔剛論争の収束
前項に述べた北伊豆地震が起きたのが昭和 5 年の 11 月、そして前々項に述べた「真島健三郎 vs. 武藤清」の論戦があったのがその翌年の昭和 6 年です。
ところで、昭和 6 年といえば満州事変が勃発した年です。これ以降、日本は坂を転げ落ちるように陸軍を中心とした軍閥政治へ向かっていきます。それが柔剛論争と何の関係があるのか、と言われると私にもよく分かりませんが、とにかく「そういう時代」だったのです。
そんな中で、昭和 7 年に還暦を迎えた真島は海軍省の職を辞して隠居生活に入ります。ここまで見てきたように、柔派の主だった論客は真島しかいないのですから、彼が第一線を退けば柔剛論争は自然に収束を迎えることになります。
しかし、その真島が一度だけ、「元海軍省建築局長」という肩書きで「建築雑誌」に登場しています。昭和 10 年 10 月の「棚橋君の新説を一読して感想を述ぶ」です。
彼はここで、「長く隠居生活をしているため、この問題(柔か剛か)が最近どのように進展しているのかは知らないが、しかし私自身、全く興味をなくしたわけではない」と前置きしながら自説を展開しているのですが、それにしても、「棚橋君の新説」とは何のことでしょう?
棚橋諒(たなはし・りょう)は明治 40 年生まれで、その当時は京都帝国大学に籍をおく工学博士でししたが、真島がいう「新説」とは、彼が昭和 10 年 5 月に「建築雑誌」に発表した「地震の破壊力と建築物の対震力に関する私見」という論文のことです。
彼はその中で、地震の破壊力を「運動エネルギー」と捉え、一方、それに対する建物の耐力(原文では「対震力」)を「破壊にいたるまでに貯えうるポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)」と考えています。前者よりも後者が大きければ建物は破壊に至らないのです。さらに、地震の運動エネルギーはその最大速度によって決まる、としています。
あらためて言うまでもなく、これは現在の「エネルギー法」の考え方につながるものです。また、地震と建物の関係を「力」ではなく「エネルギー」の観点から見るという考え方は、現在の「保有水平耐力計算」や「限界耐力計算」にも受け継がれています。注)
注)
ただし、当時考えられていたのは弾性範囲内の話で、弾塑性範囲までを視野に入れたものではありません。棚橋はこれと平行して塑性範囲を含めた研究を進めていたのですが、この時点では、それを明確に理論化するには至っていませんでした。
これに対し、真島は先の論文で、「やっと柔派の仲間があらわれた」と歓迎しています。なぜならば、下図に見るように、もし作用する地震力が同じであるのならば、柔構造の方が剛構造に比してより多くのポテンシャルエネルギーを持つことになるからです。
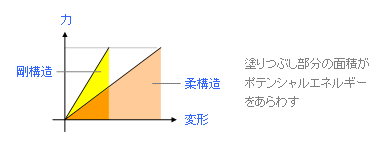
真島はこれにつづけて、「しかし、実際問題として重要なのは地震力の大きさであり、それを抜きにしてポテンシャルエネルギーの大小のみで耐震性を論ずることはできないだろう」としています。
しかしどう見ても、ここには、真島が棚橋の説を無理やり自らの「柔構造優位説」に引き入れて論じようとしている趣きがあります。
そこで棚橋は、昭和 11 年 2 月の「真島博士の批評に答ふ」(建築雑誌)で、「私がとっている立場は剛構造説でも柔構造説でもなく、ポテンシャルエネルギー説である」とクギをさすことになります。
たしかに、「エネルギー」という考え方を導入すれば、「剛構造」「柔構造」という立場にとらわれず、それらをシームレスに眺め渡すことができるのは間違いありません。
さて、「それでどうなったのか」ですが、残念ながら(少なくとも私たちが知りうる範囲では)「どうにもならず、そのまま終わってしまった」ように見えます。注)
注)
ただし上記の棚橋の論文に対しては、その後、剛派の側からの反論も出ています。
佐野一党の河野輝夫による「剛構造論を支持す」(昭和 10 年 12 月)がそれですが、これに対しても棚橋は、上に述べたのと同様の主張(私は剛派でも柔派でもない)を繰り返します。しかしこのあたりは、柔剛論争全体からみれば、その末期に起きた「さざなみ」のようなものでしょう。
社会史の上では、その後は一直線に太平洋戦争に突き進んで行きます。建築構造史の上では、(戦時中の非常時立法のようなものを除けば)次のエポックは戦後の「建築基準法」まで待つことになりますが、これが剛派の主張に全面的に沿ったものであったことは言うまでもありません。
さらにその後、という話はここではしません。
ちなみに真島健三郎は、上記の論文を寄稿した数年後の昭和 16 年、つまり太平洋戦争開戦の年に生涯を終えています。
完 ( 文責 : 野家牧雄 )