続々・建築基準法はどう変わったのか
2007 年 6 月 20 日の改正建築基準法の施行にむけて、5 月 18 日に大量の国土交通省告示が公布されました。どれくらい大量かというと、ざっと見渡したところ、第 592 号から 628 号までの連番が振られているようなので、計 30 本を超えていることになります。
といっても、べつに建築構造計算の改革がなされたわけではありません。その内容の多くは、設計者に対して「都合のいい仮定にもとづいた都合のいい設計」を行うことを戒めたものです。
一方、立場を変えて、これを構造計算書を審査する側からみた場合には、これにより「審査基準が統一されて審査業務が円滑化する」という効果がもたらされることになります。つまり、割り切った見方をするならば、これは「構造計算書の審査マニュアル」である、ということもできそうです。
ここでは、これらの告示のうち、多くの設計者にとって関心が高いと思われる「許容応力度設計」に関するものをピックアップして簡単な説明を加えています。
目次がわりにその項目をしるすと以下の通りです。
第592号 建築物の構造方法が安全性を有することを確かめるための構造計算の方法を定める件
第593号 建築基準法施行令第36条の2第5号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件
第594号 保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件
第595号 既存告示の改正
第596号 既存告示の改正
第597号 既存告示の改正
第598号 既存告示の改正
このうち、設計者にとって最も重要度が高いのは(太字にしている)「第593号 建築基準法施行令第36条の2第5号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件」と「第594号 保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件」です。注) はっきり言ってしまえば、その他はほとんど関係ありません。
注)
この二つについては、弊社製品「構造計算入門 第二版」の「新着情報」にて全文を読むことができます。
なお、第 599 号以下は、プレストレスコンクリート造や膜構造等の特殊構造に関わるもの、あるいは既存告示の字句の修正というような内容なので割愛します。また、ここで取り上げているもののうちでも、木造やステンレス鋼等に関わる部分については説明を省いています(理由は、時間がなくてそこまで手が回らないため)。
第592号 建築物の構造方法が安全性を有することを確かめるための構造計算の方法を定める件
これまで一般に行われていた応力解析や保有水平耐力の解析手法(固定モーメント法・たわみ角法・増分解析法・節点振り分け法その他)を追認した、という内容で、とくにどうというものではありません(このような告示が必要な理由についてはよく分かりませんが)。
第593号 建築基準法施行令第36条の2第5号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件
「建築基準法施行令第36条の2第5号」とは「建築基準法第20条の第2号に定める建築物」を定義しているものです。その「建築基準法第20条の第2号に定める建築物」とは、ようするに「ルート 2 あるいは 3 の建物」なんですが、一体なぜそんなことが改めて問題にされるのかというと、改正建築基準法では、それに該当する建物の審査は「適合性判定機関」が行うことになっているからです。
つまり、この告示の主旨は「適合性判定をようする構造計算とはどのようなものなのか」ですが、それをいうために、ここでは「適合性判定をようしない構造計算とは何なのか」を説いています。「ここに書かれているような建物以外は適合性判定をようする」のです。
ところで、私たちの知るところでは「ルート 1 以外の建物は適合性判定にまわる」のですから、ということは、ここには「適合性判定機関にまわらないルート 1 の建物とは何なのか」の定義が書かれているはずです。で、よく読んでみると、その通りのことが書かれています(私がわざと話をヤヤコシクして伝えているように聞こえるかもしれませんが、そんなことはありません、そのように書かれているのです)。
RC・SRC造の建物の「ルート 1 」の定義は従来と変わりません。しいて言えば、これまで「2001年版 建築物の構造関係技術基準解説書」の「技術慣行」の中にあった「設計せん断力の割増し率」の値がここに移行していることくらいでしょうか。
鉄骨造の建物の場合は従来の規定に加え、冷間成形角形鋼管を使用したものについては、「冷間成形角形鋼管設計施工マニュアル」という本にあった「ルート 1 の場合の地震時応力の割り増し」がこの告示の本文に「格上げ」されています。注)
注)
「2001年版 建築物の構造関係技術基準解説書」あるいは「冷間成形角形鋼管設計施工マニュアル」の内容の法律への「格上げ」という事例は、今回の告示群の随所に見られます。
ここでちょっと注目しておく必要があるのは、鉄骨造の場合には、ルート 1 が二つに枝分かれしている(従来のもの+新しいもの)ことです。
従来のルート 1 における建物規模制限は、
地上階の階数が 3 以下
高さが 13m 以下
軒の高さが 9m 以下
スパン長が 6m 以下
延べ床面積が 500m2 以下
でしたが、この他に、
地上階の階数が 2 以下
スパン長が 12m 以下
延べ床面積が、2 階建ての場合 500m2 以下、平屋の場合 3000m2 以下
という建物に適用される別ルートが新設されています(これを見るかぎり、スパンの大きな工場とか倉庫のようなものを想定しているようですが)。
このような建物に対する計算規定は、従来のルート 1 にあるものがすべて適用されますが、それに加えて、以下のようなことを要求しています。
偏心率が 0.15 以下であること
幅厚比の規定
梁の仕口部の保有水平耐力接合
梁の継手部の保有水平耐力接合
梁の保有水平耐力横補剛
柱脚部の保有水平耐力接合
つまり、「層間変形角」と「剛性率」の規定を除いて、実質的にはルート 2 の設計を要求していることになります。
なお、告示本文にはありません(もともと「計算ルート」という呼び方は法令には出てきません)が、前者、つまり従来のルート 1 を「ルート 1-1 」、今回新設されたものを「ルート 1-2 」と呼ぶことになるようです。もちろん、このどちらかの要件を満たしていれば「ルート 1 」とみなされ、適合性判定にはまわりません。
第594号 保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件
先ほども言いましたが、今回公示された各種の告示の中で、設計業務におよぼす具体的な影響という点からいうと、これが最も重要なものです。
表題にあるとおり、保有水平耐力計算(つまりルート 3 )と許容応力度等計算(つまりルート 2 )の具体的な計算方法について言及したものですが、と言っても網羅的・系統的に記述されているわけではなく、いくつかの「設計上の留意点」をトピックとして取り上げる、という書き方になっています。以下、その記載順にしたがって簡単に見ていくことにします。注)
注)
ここで、どうもよく分からない点があるのですが、この表題から推すかぎり、この内容は保有水平耐力計算(ルート 3 )と許容応力度等計算(ルート 2 )について言及しているもので、「ルート 1 については適用されない」と考えてよさそうです。
しかし、ルート 1 の建物の要件を定めた前述の第 593 号において耐力壁の開口周比に言及している部分があり、そこには「告示 594号 に規定する・・・」と書かれています。ということは、少なくとも、以下に述べる耐力壁の開口の考え方はルート 1 にも適用されることになります。
設計者としては、この告示にあるもののうち、とくにルート 2 ないし 3 に特化されたもの以外は「ルート 1 にも適用される」と考えておいた方が「無難」なような気もするのですが・・・。
耐力壁とみなしてはいけない開口
「開口部の上端を当該階の梁に、かつ、開口部の下端を当該階の床版に接するものについてはこれを一の壁として取り扱ってはならない」とあります。下図の左にあるような、いわゆる「そで壁」のことを言っているのです。このような壁は、いくら開口周比が規定を満たしていても耐力壁 注) にはなりません、ということ。
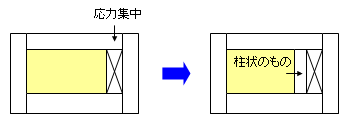
これはおそらく、上のような壁の場合、壁の上下のシェアスパンの短い梁に大きな応力集中が起きるはずなのに、その梁が「耐力壁の周辺梁」とみなされて設計がおざなりにされる、ということを戒めたものと思われます。ただし、「耐力壁とはみなせない」ではなく「一の壁(イチのカベと読むのか?)として取り扱わない」という言い方をしているのは、これを上図右のように開口際に柱状のものを設けて「耐力壁+境界梁」という明快な構造にするのならいいですよ、という「含み」をもたせているのでしょう(たぶん)。
注)
昔から、国交省系列の文章では「耐力壁」といい、日本建築学会系列のものでは「耐震壁」と言っています。この文章は告示の説明なので「耐力壁」としてますが、しかし、どうみても「耐力壁」と「耐震壁」は同じものです。どちらかに統一する訳にはいかないものなんでしょうか?
そういえば、戦後のある時期まで、英語の Planet の訳語を東京大学系列の学者は「惑星」とし、京都大学系列の学者は「遊星」として、両者とも長い間ガンとして譲らなかった、という話を何かの本で読んだことがあります。あるいは、それに似たような事情があるのでしょうか?
耐力壁の開口低減率
耐力壁とみなすための条件(開口周比が 0.4 以下)、開口による剛性低下率の計算式、開口低減率の計算式がそれぞれ記載されています。これは日本建築学会のRC規準にあるものと同じです。
ただし、注意したいのは、開口低減率を定めるための条件として「開口の高さによる低減」の項が追加されていることです(これはRC規準にはないがSRC規準にはある項目です)。
つまり、開口低減率は「面積による低減」「幅による低減」「高さによる低減」の三つのうちの一番小さいものをとることになります。
壁に片開きのドアの開口がひとつだけある、という下図のようなケースはよくあります。これは通常のスパンと階高のもとでは開口周比が 0.4 以下になり、耐力壁になります。しかし、このような壁の許容耐力をもとめると、たいていは「高さによる低減」で決まるため、従前のやり方(高さによる低減を考えないもの)に比べて大幅に耐力が小さくなるので注意しておくべきです。
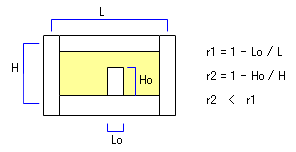
部材の剛性低下
一次設計において、コンクリート断面(とくに耐力壁)のひび割れによる剛性低下をあらかじめ見込んでおく、という設計はしばしば行われます。この告示では、そのようなやり方を否定しているわけではありませんが、ただし「あくまでも弾性域内の話ですよ」とクギをさしています。
どういうことかというと、RC部材の力と変形の関係は下図にあるような「ひび割れ」と「降伏」を折れ点としたもので一般にあらわされますが、この部材が弾性限界に達した時の剛性低下率(降伏時剛性低下率)はここにある通りです。これが弾性域でとりうる最小の剛性低下率なのですから、一次設計でこれを下回る値を使うことは部材の塑性化を許容していることになります。「それはおかしいよね」と言っているのです。
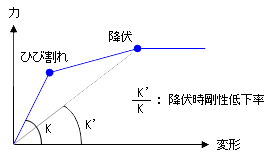
基礎ばね
地盤や杭の変形を考慮して、応力解析時に「基礎ばね」を設けることがありますが、これについても、前項同様「あくまでも弾性域内の話」であり、さらに、その値は「きちんとした調査と技術的な根拠にもとづいて定めること」としています。
耐力壁の負担が大きい階の柱
耐力壁に多くを期待するような建物においては、柱にもある程度の余力をもたせなさい、ということを言っています。
具体的には、「耐力壁の地震時せん断力の負担率が 50% を超えるような階においては、その階の柱が長期軸力の 25% に相当するせん断力に耐えるように設計すること」としています。
4 本柱の建物
(これはよく言われてきたことですが)建物の隅部の柱には、設計時に仮定した XY 方向以外から地震力が作用した場合、仮定よりも大きな応力が発生します。とくに、4 本しか柱がないような建物の場合は、そのような想定外の力が建物に致命的なダメージを与える可能性があります(いわゆる「冗長性のない構造物」)。
そこで、「 4 本柱の建物 注) の場合は、XY 方向以外から作用する地震力についても考慮するか、もしくは地震力を 1.25 倍以上にして設計しなさい」としています。
注)
もっとも、告示の文面には「 4 本柱」というような「俗」な表現はなく、「隅部の柱が負担する長期軸力がその階が支える建物の重量の 20% を超えるようなもの」となっているのですが、「ようするに 4 本柱のこと」と考えて差し支えないと思います。
突出物の地震力
屋上突出物や外壁から突出した屋外階段等については局部震度 1.0 以上で設計すること。また、片持ちのバルコニー等のように外壁から突出するもの(その長さが 2m を超える場合)については鉛直震度 1.0 以上で設計すること。
層間変位の定義
層間変形角あるいは剛性率の検証にもちいられる「層間変位」とは、「各階の上下の床版と壁または柱とが接する部分の水平方向の変位の差」であると定義されています。「層間変位」とは「層間変形角の分子」のことですが、分子がそうであるのならば、「層間変形角の分母」の方も下図にあるような「上下階の床版間の距離」でなければならないことになります。
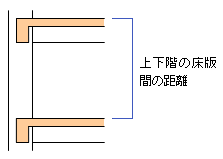
従来、層間変形角の分母の値として「構造階高」を採用することが多く行われていました。そのため、たとえば典型的な例として鉄骨造の建物の一階を考えると分かりますが、地中梁のせいを大きくして構造階高を大きくすると層間変形角の分母が大きくなり、層間変形角そのものの値を小さくすることが可能になります。
しかし、層間変形角の制限というのは、そもそも「仕上げ材等の非構造部材の過大な変形を抑制して建物の使用性能を維持する」という考え方からきているものなのだから、そこに「構造階高」を持ち込んでくるのはおかしいではないか、というような発想にもとづく内容かと思われます。
増分解析の終了条件
これまで行われてきた最も一般的な保有水平耐力の計算方法というのは、「増分解析によって、設計者が指定したある条件(層間変形角が一定の値に達する、せん断破壊部材が発生する等)に達するまで建物を押していき、その状態に達した時点で解析を終了し、その状態から<保有水平耐力>と<必要保有水平耐力>をもとめる」というものです。
このうちの「保有水平耐力」については、建物が本来の意味での「崩壊」に達する以前のどの状態で評価しようとも、それは安全側の設定(本来の耐力よりも値を低く見積もる)になるので問題はありません。
問題は「必要保有水平耐力」の方で、そもそもこれはどのような値なのかというと、「建物が塑性状態に達した後でどの程度まで変形に追従できるのか」を評価するものです。したがって、建物が塑性状態に達する前に解析を打ち切り、その状態をもとに評価しようとすると、場合によっては危険側の仮定(建物の性能を本来よりも高く見積もる)に立つことになってしまいます。
そこで、「設計者が指定したある条件により<保有水平耐力>に達したととみなされる場合でも、解析を終了せず、建物が崩壊に達するまで押し続け、その最終状態をもとに<必要保有水平耐力>をもとめなさい」ということになりました。
これを建物の力と変形のグラフ上にあらわすと下図のようになります。
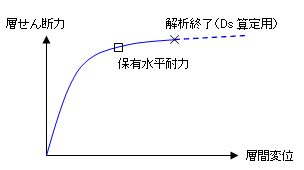
増分解析時の外力分布
保有水平耐力を増分解析によりもとめる場合の外力分布は、原則として「一次設計時にもちいた Ai 分布にもとづく地震力」とすること、とされています。
この他に、これまでしばしば行われてきた方法として「必要保有水平耐力にもとづいた外力分布」をもちいる、というものがあります。必要保有水平耐力とは建物の「応答値」をあらわすものですから、この考え方自体がおかしいわけではありませんが、しかしその場合でも、「 Ai 分布にもとづく地震力に対する安全性を確認しておく必要がある」とされています。
ルート 3 における部材の脆性破壊の防止
ルート 3 の場合の部材の脆性破壊防止のための検証法について書かれています。これは今までも慣用的に行われてきており、とくに目新しいものではありませんが、簡単にふれておきます。
「冷間成形角形鋼管設計施工マニュアル」にあった記述(柱・梁 / パネル耐力比等)がここにそのまま移行されています。
RC造のせん断破壊の判定に際してもちいる安全率のとり方が以下のようになっています。
両端ヒンジの梁 : 1.1, それ以外の梁: 1.2 (ただし長期せん断力を考慮する)
両端ヒンジの柱 : 1.1, それ以外の柱: 1.25
耐力壁 : 1.25
また、RC部材の終局せん断強度式が掲げられていますが、ここにあるのは、いわゆる荒川式で係数が 0.068 のものです。
第595号 (既存告示の改正)
既存の告示(昭和55建設省告示第1791号「特定建築物の地震に対する安全上な構造計算の基準を定める件」)の改正。ようするに「ルート 2 」の建物が満たすべき要件をさだめたもの。
「冷間成形角形鋼管設計施工マニュアル」にあった「柱梁耐力比」の検証が追加されている。
鉄骨部材の「幅厚比」の規定が、従来は「 400N 級」と「 490N 級」に分けて定められていたが、これを「係数×√ ( 235 / F ) 」という形式に一般化してあらわしている(実質的な値は従来と同じ)。
RC部材の設計せん断力の割増し等についての規定が「2001年版 建築物の構造関係技術基準解説書」の「技術慣行」の中にあったが、これがそのまま告示本文に移行している。
第596号 (既存告示の改正)
既存の告示(昭和55建設省告示第1792号「 Ds 及び Fes を算出する方法を定める件」)の改正。
実質的には何も変わらないが、前項に述べたとおり、鉄骨部材の幅厚比による種別の規定が、従来は「 400N 級」と「 490N 級」に分けて定められていたが、これを「係数×√ ( 235 / F ) 」という形式に一般化してあらわしている(実質的な値は従来と同じ)。
第597号 (既存告示の改正)
既存の告示(昭和55建設省告示第1793号「 Z の数値、Rt 及び Ai を算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準を定める件」)の改正。
地盤や杭の変形を考慮した状態で建物の振動特性を精算すると固有周期が長くなり、結果として設計地震力が小さくなるが、そのようなやり方を牽制したもので、「そういう場合は地盤や杭が変形しないものとして計算しなさい」としている。
第598号 (既存告示の改正)
既存の告示(平成12建設省告示第1457号「 Td、Bdi、安全限界変位、Ts、Bsi、Fh 及び Gs を計算する方法ならびに・・・」)の改正。
限界耐力計算関係のもの。内容紹介は割愛。
(終わり)