|
たとえ固有値解析等の方法で固有周期を「精算」したとしても、それが建物の「実際の固有周期」なのかといわれると心もとない部分がある。その理由は前項で書いたように、計算結果が地盤や基礎のモデル化等のもろもろの与件に左右されるためである。
一方、実在する建物の固有周期は、人為的に振動を与えたり、あるいは常時微動を観測することによって計測できる。そこで、それらの計測結果を収集し、そこに何らかの傾向を認めることによって建物の固有周期を推定する、という試みがかなり昔から行われていた。
日本建築学会「建築物の耐震設計資料」 ( 1981年 ) には、そのような主旨によるさまざまな推定式――全部で13個もある――が紹介されている ( P.137-142 ) が、中でも最も単純なのは「谷口式」と呼ばれるものだ。ここでは、固有周期を T ( 秒 )・建物の階数を N とした時、両者の間に
T = 0.07 〜 0.09 N
の関係があるとしている。
ここで各階の階高を 3m とすれば、建物の高さ H ( m ) は 3N なので、上の式から
T = 0.02 〜 0.03 H
という現行規準の式――以下、「現行式」と記す――とほぼ同じようなものが得られることになる。
おそらく、現行式の出所はこのあたりかと思われる。建物の階数や高さが大きくなるほど固有周期が伸びるのは間違いないが、それにしても、この式はどこまで信用できるのだろうか?
前出の「建築物の耐震設計資料」には、建築学会で収集した実在建物の固有周期の計測値 ( S造 10 件・RC/SRC造 49 件 ) を建物の高さごとにプロットしたグラフが載っている ( P.276 ) ので、それを下に示しておこう。
固有周期 - 軒高 ( S造 )
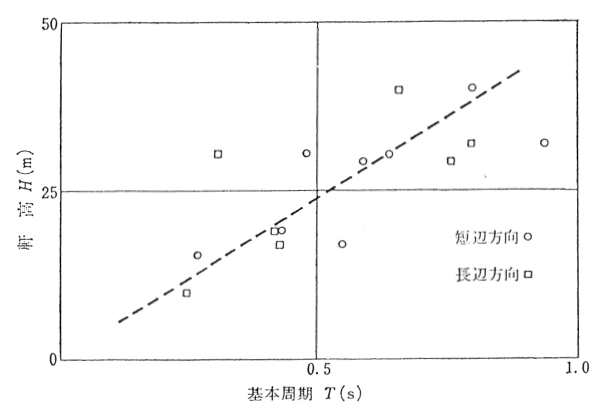
固有周期 - 軒高 ( RC/SRC造 )
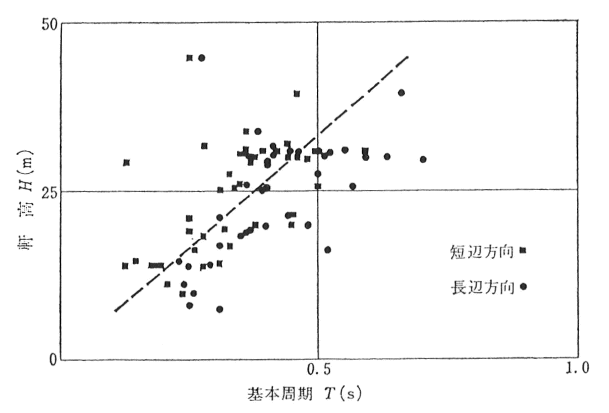
ここから得られる回帰式がグラフ中に破線で描かれているが、以下の通りである。
T = 0.021H : S造
T = 0.015H : RC/SRC造
上の係数は現行式の 70 ないし 75% ほどの値になっているが、いかんせん、これではサンプル数が少なくて心もとない気がする。
太田外気晴・石田正美「建築物の固有周期による耐震性能の評価法」という論文 ( 第5回 構造物の破壊過程解明に基づく地震防災性能向上に関するシンポジウム論文集 2004年3月 ) に目を通していたら、日本建築学会が 2000 年に実在建物 ( 計 205 棟 ) の固有周期の計測値を網羅した CD-ROM を出していることを知った。私自身は未見だが、同論文中にその結果をまとめた表と考察があるので紹介しておく。
下に掲げたのは、建物の高さをパラメータにして固有周期の実測値をプロットしたもの――さきほどとは縦軸・横軸が逆になっていること、ならびに対数グラフになっていることに注意――である。
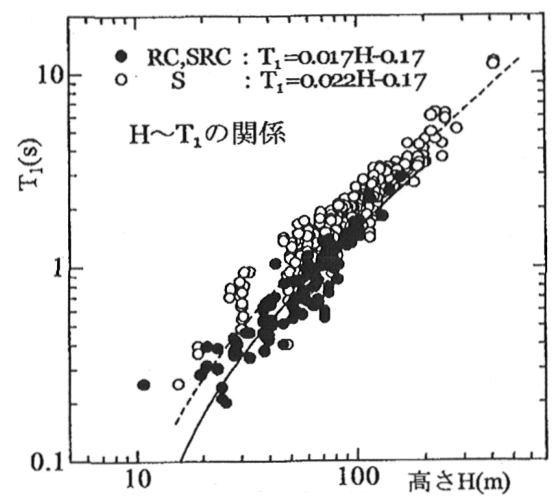
ここから得られる回帰式 ( 1次式 ) は以下の通りで、やはり現行式よりは小さな値になる。
T = 0.022H - 0.17 : S造
T = 0.017H - 0.17 : RC・SRC造
ここまで見てきたように、実測した固有周期の値は設計値よりも小さくなっている。
ここでいう「設計値」は略算によるものを指しているが、精算した固有周期は略算よりも大きくなる傾向があるので、「実測値は設計値よりも小さい」というのは一般的な傾向と考えてよさそうである。このあたりについては日本建築学会「地震荷重―その現状と将来の展望」 ( 1987年 ) でいくつかの研究成果が披露されている ( P.156-158 ) ので、以下、それに頼って書くことにする。
ここでは、実測値が小さめになる理由を、「振動実験や常時微動の測定から得られる実測値はごく微小な振幅のもとで求めているいるのに対し、設計値は、強震によって生じる大きな振幅を前提として求めたものだから」であるとしている。
そこでこんどは、建物に設置された強震計の記録から「大きな地震を受けて実際に揺れている建物の固有周期」を推定する試みがなされることになる。
その結果によれば、強震を受けている建物の固有周期は、振動実験から得られる値に比べて 2 から 3 割程度は伸びるらしい ( 前出の論文「建築物の固有周期による耐震性能の評価法」には、建物の最大応答時の周期が初期周期の 2.7 倍になったという例も報告されている )。
つまり「地震前」と「地震中」では固有周期が変わるのだが、さらにもう一つ、ここには「地震後」という値も存在する。
とくにコンクリート系の構造物の場合、強震により部材にひび割れが発生すると剛性が落ちるので、固有周期が変わってしまうことは容易に察しがつく。強震を受けた後の建物の固有周期は、一般に初期周期の 1.2 から 1.5 倍くらいの値になるらしい。
私たちは建物の「固有周期」という語感から、これを「その建物に固有の、一定不変のもの」と思いがちだが、ここまで見てきたように、この値は「地震前 → 地震中 → 地震後」を通じ、かなりの幅で変動する。だから精算であれ略算であれ、「これが正しい」と一概にいうことはできないのだ。
先に、「このコンピュータ万能の時代に、なぜ粗雑な略算値が広く使われるのか」というような疑問をていしたが、このような観点から考え直してみると、固有周期を略算によって大雑把に捉え、そこから「設計の目安」とすべき地震力を「ざっくり」と設定する、という現在のやり方は意外に的を得た方法なのかもしれない、という気がしてくる。なにしろ、私たちはこのやり方を 30 年以上も続けてきて、その間に何か問題があったのかと問われれば、少なくともいまの時点では「別に何も」と答えざるを得ないのだ。
前へ | 1 | 2 |
( 文責 : 野家牧雄 )
|