建築構造・まぎらわしい用語集
目次
「荷重」と「外力」 「耐力壁」と「耐震壁」 「筋かい」と「ブレース」 「梁」と「はり」
「耐力」「強さ」「強度」 「降伏曲げ」「終局曲げ」「全塑性曲げ」
「荷重」と「外力」
建築構造に関わる仕事をやっていると、「荷重及び外力」という言い回しに頻繁に遭遇するが、これが昔から気になって仕方がない。
これの起源は建築基準法施行令の第 8 章第 2 款の表題(荷重及び外力)あたりになるのだろうが、当然ながらその解説本、建築構造関連の参考書、あるいは日本建築学会の「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」などでもこの用語は使われている。
一般に「 A 及び B 」という言い方をする場合、A と B はそれぞれ独立した集合をなしていると考えられる。だから、「小学生及び中学生」なら分かるが、「小学生及び生徒」と言われたら首を傾げてしまう。
つまり、「荷重及び外力」と言うからには、「荷重」と「外力」は「別のもの」のはずなのだが、ではどのように「別のもの」なのだろうか?
その答えは簡単である。
建築基準法施行令の第 83 条(荷重及び外力の種類)では、「建築物に作用する荷重及び外力」として
固定荷重
積載荷重
積雪荷重
風圧力
地震力
の五つをあげている。
見ての通り、ここにある前の三つが「荷重」、後の二つが「外力」なのである。具体的にいうと、地球の重力加速度を原因とし、私たちがそれを「重さ」として感じることができるものを「荷重」、それ以外のものを「外力」と分類していることになる。「荷重」の第一義である「荷の重さ」にこだわったのであろう。
それにしても、「風荷重」「地震荷重」という言い方だってあるし、げんに使われてもいる。しかし、少なくとも法令の上ではこの用語は存在しない。「2007 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」を検索しても「風荷重」「地震荷重」はない。「風圧力」「地震力」のみである。
では、「風荷重」「地震荷重」という言い方は、いつ頃から誰が使い始めたのか?
それはよく分からないが、前から使われていたことは確かである。その証拠に、日本建築学会「建築物荷重指針・同解説」ではもっぱら「風荷重」「地震荷重」なのだが、その本の 1981 年版の 29 ページに以下のような記述があるので以下に引用しておく。
風荷重については、従来「風力」あるいは「風圧力」という言葉が使われ、地震荷重は「地震力」と呼ばれることが多かったようである。しかし、本来「荷重」という言葉と「外力」という言葉の意味の相違は明確でなく、風・地震以外に就いてはすべて「荷重」という言葉が慣用になっているので、ここでは「風荷重」「地震荷重」という言葉を用いることにした。
ところで、その「建築物荷重指針・同解説」だが、ここに興味深い用語が登場している。
「温度荷重」である。
私たちは「温度応力」という用語(外気の温度差によって生じる部材の伸縮に伴う応力)はよく使うが、その原因となるものを「温度荷重」と呼ぶ習慣はあまりないかもしれない。しかしここでは、
部材の応力に変化をもたらす原因となるものはすべて荷重と呼ぶ
ことにしている。だから「温度荷重」なのである。
一方、これを「温度力」と呼ぶのはどうだろうか?
かつて「老人力」という言葉が流行したことがあったし、また「人間力」という造語を耳にすることもあるので、そういう意味では、「温度力」――温度差が潜在的に持っている力――も「あり」かもしれないが、しかし工学用語としては何か変な気がする。
と言うのも、私たちは、「力」というのものは必ず何らかの「方向性」を持っていると考えるからである。
風や地震を原因とするものを「力」と呼ぶのはよく分かる。風とは「空気が流れること」、地震とは「地面が揺れること」であり、それ自体は「力」ではないが、しかしそれを原因として何らかの「力」が生まれた時、私たちはそれを「方向」「大きさ」という属性とともに認識する。それが「外力」なのである。
しかし、「外気の温度差」には「方向」という属性がないので、これを「外力」と呼ぶことには抵抗がある。
このような事情は「温度荷重」でも変わらないはずだが、しかし、「温度力」ほどの違和感がない(私だけの個人的な感じ方かもしれませんが)のはどうしてだろうか?
たぶん、「荷重」という用語は「力」ほどの具体的なイメージを喚起せず、より抽象性が高いからではないかと思う。
一方、法令にある「荷重及び外力」という分類に従うと、先に述べたように、ここでは「荷重」という用語の範囲を限定しているため、「温度応力を生じさせる原因となるもの」についてはどちらのカテゴリーにも属さないことになってしまう。あえて分類すれば「外力」ということになるのだろうが、これも先ほど述べたような理由により、どうもシックリこない。
以上のようなわけで、私としては、「荷重及び外力」という悩ましい言い方はやめて、たんに「荷重」と呼んだ方がスッキリするのではないかと思うのですが、どんなものでしょうか?
「目次」に戻る
「耐力壁」と「耐震壁」
「広辞苑第 6 版」によると、耐力壁とは「建物の壁のうち、構造体の一部として耐力を分担する壁面」とされている。
この用語は、ビル構造物というよりも、主として木造建築物を対象に現在も広く使われているもので、そういう意味では、木造建築物の用語がそのままビル構造物に転用されたものと考えておくのが自然かもしれない。
木造建築物における耐力壁とは「(地震や風による)水平力に抵抗する壁」のことで、「筋かい」と「面材」に大別される。
木造建築物以外のものについていえば、主として「筋かい」は鉄骨構造物、「面材」はコンクリート系構造物に使われており、鉄骨造の筋かいを「耐力壁」と呼ぶ習慣はあまりない。そのため、法令の上でも、鉄骨構造物については「筋かい」、コンクリート系構造物については「耐力壁」の用語を当てるようである。注)
注)
昭和 55 年建設省告示第 1792 号(平成 19 年国土交通省告示第 596 号にて改正)の「第 3 柱及びはりの大部分が鉄骨造である階について Ds を算出する方法」の中に「筋かい(耐力壁を含む)」という記述がある。
このような書き方をするのは、「筋かい」と「耐力壁」を分けて考えているからだろう。なお、ここにいう「耐力壁」とは、いわゆる「鉄板耐震壁」のようなものを指したものと思われる。
「耐力壁」によく似た用語に「耐震壁」がある(ちなみに、「広辞苑第 6 版」には「耐力壁」はあるが「耐震壁」の項目はない)。
この言葉を「発明」した――と言うよりも、耐震壁というものを「創案した」と言うべきかもしれないが――のは早稲田大学の内藤多仲である。望月重「耐震壁ものがたり」(鹿島出版会)によると、「耐震壁」という用語は、日本建築学会の機関誌「建築雑誌」の 1923 年 1 月号に掲載された内藤博士の論文「架構建築耐震構造論(四)」の中で最初に使われたものらしい。
これはおそらく、(推測に過ぎないが)木造構造物を対象に流通していた「耐力壁」という用語との差別化を図る目的でこしらえた用語だったのではないかと思う。
しかし、法令の中に「耐震壁」は登場しない。もっぱら「耐力壁」である。
一方、日本建築学会から出されている各種の規準ではこの両者を使い分けている。
ラーメン構造の中に一体で打ち込まれ、水平荷重(地震力)のみを負担するのが「耐震壁」で、それに対し、壁式構造にある壁のように、水平荷重ばかりでなく鉛直荷重も負担するものが「耐力壁」である。
結局、ラーメン構造の中にある壁についていえば、法令ではこれを「耐力壁」と呼び、日本建築学会はこれを「耐震壁」と呼んでいることになる。
これらはまぎれもなく「同じもの」を指しているのだが、どちらかというと、設計者の間に広く浸透しているのは「耐震壁」の方ではないだろうか? その証拠に、「独立耐震壁」とか「連層耐震壁」という言葉はよく耳にするが、これを「独立耐力壁」「連層耐力壁」と言う人はあまりいない。
「目次」に戻る
「筋かい」と「プレース」
前項の「耐力壁」「耐震壁」と同様に「同じものを指す二つの用語」として、「筋かい」――「筋交い」「筋違い」「筋違」とも書く――と「プレース」がある。
一般的な慣習としては、木造建築物の場合は「筋かい」、鉄骨建築物の場合は「プレース」としていることが多いだろう。これは、もともと「筋かい」という用語が木造建築物を対象に使われていたため、それとの差別化を図る目的で、鉄骨建築物の方ではあえて「プレース」という横文字を選んだ、というような事情かと思われる。
しかし、法令の上ではすべて「筋かい」で、「プレース」という用語は使われていない。
では一方、日本建築学会の諸規準の方ではどうなのかと思って調べてみたら、こちらもやっぱり「筋かい」でした。「筋かい(プレース)」という書き方をしている箇所もあるが、基本用語は「筋かい」なのである。各種の設計例でもすべて「筋かい」を使っている。
それにしても、鉄骨建築物の「実際の」構造計算書や構造図面ではほぼ例外なく「プレース」が使われているのだから、これはこれで不思議な話である。
「目次」に戻る
「梁」と「はり」
法令の話題をさらに続けるが、ここで最も気になる言い回しが「はり」である。もちろん「梁」のことだが、なぜ平仮名で書くのか?
私はてっきり、その理由は「この字が常用漢字表にないから」だと思っていたのだが、そういうわけではないらしい。
その証拠に、建築基準法施行例第 56 条には「臥梁(がりょう)」という言葉が漢字のまま堂々と登場している(もちろん「臥」も常用外)。ということは、常用漢字うんぬんとは関係なく、「梁」の字は「りょう」という音読みで成語の一部をなしている場合に限り使用する、というルールに従っているだけなのかもしれない。
確かに、新聞紙面でも「棟梁」という言葉はそのまま漢字で使われている――いつのことかは忘れたが、朝日新聞で見かけた――ようである。注)
注)
この他に「橋梁」というのもある。この言葉を新聞語辞典で引いてみたところ、「できるだけ使わないことが望ましく、たんに橋とすべきである」となっていた。
新聞語辞典で「はり」を引いてみると、「平仮名ではりと書くか、もしくは梁と書いて初出の部分にのみはりとルビを振る」となっている。しかし私が目にした範囲――これも朝日新聞――では、「梁」と書いた上でルビを振っており、平仮名で書かれることはあまりないようである。
また、たとえ新聞で平仮名表記されていたとしても、「建築基準法ならびに同施行令」は「新聞」ではない。
そもそも、この文章を目にする機会があるのは、建築関係者あるいは法律関係者に限られるはずである。つまり、一定のリテラシーを備えた人たちを対象にしている――そうでなければ、こんな晦渋な文章をこしらえるはずがない――のだから、この漢字を「はり」と読めない人たちに気を遣う必要はないと思う。
そのうち、この字を「はり」と読めない人たちが続々と登場して設計に携わるようになるのかと思うと、私はとても不安である(いや、ほんとに)。
「目次」に戻る
「耐力」「強さ」「強度」
JIS(日本工業規格)によれば、「耐力」「引張強さ・引張強度」「降伏点・降伏応力(上降伏点・上降伏応力)」はそれぞれ以下のように定義されている。
耐力
引張試験において、規定された永久伸びを生じるときの荷重を平行部の原断面積で除した値。降伏点が明瞭でない場合は、その代わりに耐力が用いられる。
引張強さ・引張強度
最大引張荷重(引張試験の経過中、試験片の耐えた最大荷重)を平行部の原断面積で除した値。
降伏点・降伏応力
引張試験の過程中において生じる上(かみ)降伏点及び下(しも)降伏点の総称。まぎらわしくないときには、上降伏点を単に降伏点と呼ぶことがある。
上降伏点・上降伏応力
引張試験の過程中、試験片平行部が降伏し始める以前の最大荷重を平行部の原断面積で除した値。
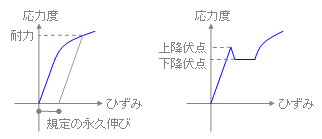
この中で最も分かりにくいのは「耐力」だが、ここにあるように、これは「降伏点が明瞭でないものに対して便宜的に降伏応力を定義するもの」と考えておけばよさそうである。一般の建築構造物に使用される鋼材は「降伏点が明瞭」なので、この値ではなく「降伏点・降伏応力」の方が使われることになる。
ところで、ここでは「応力」を「荷重を平行部の原断面積で除した値」としている。これは、私たちが行っている構造計算の用語では「応力度」ということになる。つまり、「応力」と「応力度」は同じものなのである。
少なくとも、それが JIS に則った「正式な用語法」ということになるのだが、しかしこれまでの構造計算の慣例では「応力を断面積で除したものが応力度」としているので都合が悪い。
そこで、日本建築学会「鋼構造限界状態設計指針・同解説」では、ここにある「降伏点」「降伏応力」の代わりに「降伏強さ」という新しい用語を使うことにしている。
――この「応力」「応力度」の使い分けも「まぎらわしい用語」の一つになるが、混乱を避けるため、以下の文章では、これまでの構造計算の慣例に従った「応力」「応力度」という用語の定義で通すことにします。
さて、ここでまず気付くのは、JIS では「耐力」を「応力度」として定義していることである。
しかし、私たちのこれまでの慣習によれば、「耐力」とは「応力の限界値」を表わすものである。だから「降伏点」によって限界づけられた応力を「降伏耐力」という。では、「許容応力度」によって限界づけられた耐力は何というのか?
これは現在では「許容耐力」と呼んでもいいことになっているが、そうなったのは 2007 年施行の改定建築基準法においてである。
それまでは「構造耐力上主要な部分」とか、あるいは「保有水平耐力計算」「限界耐力計算」というような使われ方をすることはあっても、「個々の部材が耐力を持っている」という認識は(少なくとも法令の上では)なかったのである。
どうしてかというと、建築基準法施行令第 82 条第三号にある通り、許容応力度計算とは、「部材に生じている応力度が許容応力度を超えないことを確かめる」もので、「許容応力度から定められる耐力を求め、それを応力と比較する」というやり方は認めていなかったのである。
しかし、多くの構造計算プログラムにおいて上のようなやり方――「断面検定」と呼ばれる――が採用されるようになってくると、さすがにこれを追認せざるを得なくなった。その結果生まれたのが「許容耐力」という言葉なのである。
次に「強度」だが、これは法令の中では「(コンクリートの)設計基準強度」「基準強度」「材料強度」のように用いられ、「応力度」を表わすものとされている。
しかし、これを「耐力」、つまり「応力の限界値」として使用しているものもある。
「2007 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」の「付録1 構造規定に関する技術資料」の中に「終局強度」「ひび割れ強度」「最大曲げ強度」などの用語が見えているが、これは間違いなく「耐力」を表わすものである。
さらには「終局強度設計」という用語もあり、日本建築学会から「鉄筋コンクリート造建物の終局強度型耐震設計指針・同解説」という本も出されている。これは絶版なので目を通していないが、同系統のものに「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説」があり、ここでも「終局強度」が使われている。
この本の「1.2 用語」には、
終局強度 : 断面あるいは部材の最大強度(抵抗力)の総称
とある。ということはつまり、これを「終局耐力」と呼んでも同じことなのだろう。
ちなみに、これら以外の日本建築学会の本では「耐力」が使われているようである(すべてに目を通したわけではないが)。
あるいは、(これまた勝手な推測に過ぎないが)これは「終局強度設計」という言葉が先行して存在していためにそれに調子を合わせたもので、それ以外の場では一般に「耐力」と呼ぶことにしているのかもしれない。
「目次」に戻る
「降伏曲げ」「終局曲げ」「全塑性曲げ」
日本建築学会「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2010」の 165 ページには、鉄筋コンクリート部材の「降伏曲げモーメント My」の算定式を 0.9・at・σy・d としている。一方、「2007 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」の 623 ページには、「終局強度」の項の下に「はりの終局曲げ強度 Mu」の算定式があり、まったく同じ内容になっている。
式の内容が同じなのだから、「降伏曲げ」と「終局曲げ」は同じもののはずである。
ようするに、鉄筋コンクリート部材の設計においては、鉄筋の「降伏点」を「終点」とし、それ以降のことは考えないことになっているので、「降伏」と「終局」は同じなのである(これに対し、たとえば木造部材のように、「降伏」と「終局」を区別する場合は、これらの値は違うものになる)。
一方、鉄骨の話になるとまた事情が違ってきて、こちらには「全塑性モーメント Mp」という値が登場する。これは部材の全断面が降伏した状態なので、前記の用語を使えば「終局曲げ」に相当することになる。
鉄骨の場合は「終局曲げ(全塑性曲げ)」と「降伏曲げ」は「違うもの」である。
この場合の「降伏曲げ」とは何かというと、部材の外縁部の応力度、つまり縁応力度が降伏点に達した時の曲げ応力の値になる。
ところで、鉄骨の短期応力度は降伏点の値そのものになっている。ということはつまり、上に書いた「降伏曲げ」は、まさしく(通常の一次設計で使われる)「短期の許容曲げ」と同じなのである。
――このような用語法は、「昔からの慣習」と言われてしまえばそれまでだが、やはり何かとまぎらわしい。
「目次」に戻る
(文責 : 野家牧雄)