増分解析法
節点振り分け法とは、「建物が崩壊にいたるに十分な数のヒンジが形成された状態」という、いわば結果だけを先取りしてもとめるものです。この結果が保証されるためには、地震力という原因が結果にうまく合致するように作用している必要があります。
しかし言うまでもなく、建物の都合に合わせて地震が来てくれるわけではありません。
そこで、「建物モデルに地震力を作用させ、その値を徐々に増やしていって建物の挙動(ヒンジの形成状況)を追跡し、建物の保有水平耐力をもとめる」というオーソドックスな手法(原因がら結果を得る)がもとめられることになりました。
これが、現在の主流となっている「増分解析法」です。
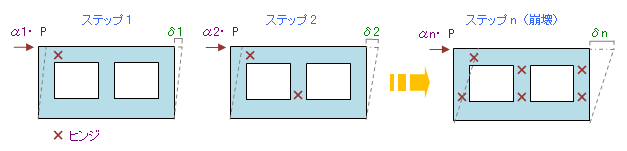
上図にあるように、地震力 P を少しずつ増やしていきながらヒンジを 1 個ずつ作っていき(これを「荷重ステップ」という)、十分な数のヒンジが形成された n ステップ目で解析を中止し、この時の αn*P を建物の保有水平耐力とする。
・・・これが増分解析法のあらましです。
いま、「十分な数のヒンジが形成された・・・」といいましたが、しかし実際には、ヒンジの数を勘定しているわけではありません。プログラム内で作用させた力 αn*P と、その時の床の水平変位量 δn の関係を下図のようにプロットして監視していると、ある時点で急激に変位量が大きくなり、このグラフが水平に近くなることが分かります。
これは、微小な力により大きな変位が生じる状態、つまり「建物の崩壊」をあらわしていると考えられるので、その直前に作用している αn*P を建物の最大耐力、つまり「保有水平耐力」とするのです。
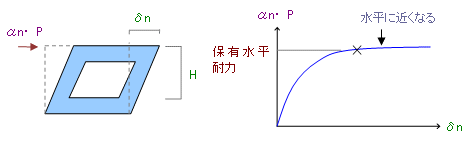
これは、建築構造物というメカニズムが力学的に不安定になった状態ですから、いわば「力学的な崩壊」です。
これに対し、「建物を構成する個々の部材がそのような大変形にはたして耐えられるのか」とか、あるいは、「建物を構成する部材が修復不能になるほどの損傷をこうむったならば、その時点を建物の崩壊とすべきではないか」というような見方もあります。こちらは、いわば「工学的な崩壊」です。
このような考え方は昔からあったわけではありません。先に述べたような、「手計算(節点振り分け法)からコンピュータ(増分解析法)の時代へ」という移り行きが背景にあります。
増分解析法をもちいることにより、私たちは初めて「建物の強震時の変形量」を知ることができるようになった。そしてそれを「問題」にし始めたわけですから、そういう意味では、冒頭に述べた、「それまでは問題にしようと思ってもできなかったことが問題にされ始めた」ことの典型的な例といえるでしょう。
この立場にたつ場合は、その階の変形角(上の図でいえば、変形量 δn を階高 H で割った値)に着目し、これがある限界値に達した時を建物の保有水平耐力と考えます。これはいわば、保有水平耐力というものの「再定義」です。
しかし、「では、その限界値とはいくらなのか」ということになると、1/50 とか 1/75 とか 1/100 とか 1/125 とか、諸説あって定まりません。そのため、告示や技術基準解説書でも、このあたりについては一切ふれていません。まだ発展途上の考え方である、と言っていいと思います。
今後どうなるかは分かりませんが、少なくとも今のところ、「建物の崩壊とは力学的な崩壊のことである」と考えておくのが無難でしょう。
