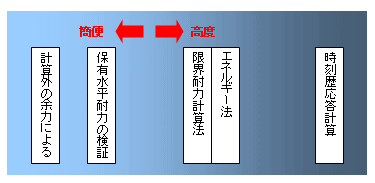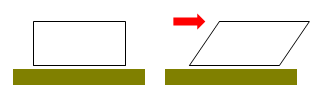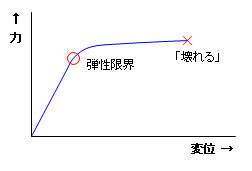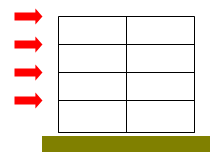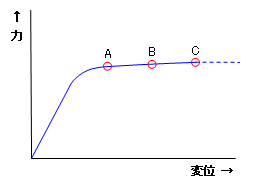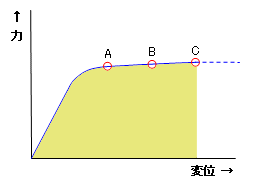強度不足、一転「安全」
3 月 7 日付けの朝日新聞の朝刊の一面に「限界耐力計算」という言葉を見つけて、わたしはいささか衝撃を受けました。大新聞の、それも一面のトップ記事でそんな建築構造の専門用語を目にするなんて、少なくともわたしはそれまで予想だにしていなかったからです。
まあ、それはともかく、そこにある 強度不足、一転「安全」 という大見出しの記事の内容を要約してみると以下のようになります。
いわゆる「耐震偽装」とされている物件で、国土交通省の発表による耐震強度の指数が 0.85 とされたマンションに対し、自治体からの依頼を受けた専門家が「限界耐力計算法」で再計算したところ、耐震強度の指数が 1 を超えていることが分かった(つまり「安全である」と証明された)。
限界耐力計算法は 2000 年から使用が認められている新しい計算法で、もちろん、現行の建築基準法に則ったものである。
これまで、公表された耐震強度の指数をもとに建て替えだ補修だと大騒ぎしてきたのに、それ自体が「やり方を変えれば結果も変わる」という性格のものであるのならば、これから一体、何を判断の拠り所にしたらいいのか?
また、この事実に対する国土交通省のコメントも載っていますが、こちらはいろいろなニュアンスを含んだ意味深長な内容なので原文のまま写しておきます。
「計算結果が食い違う場合こそ、安全性を判断するためには専門家の助言が必要になるだろう。ただ、元の強度が著しく低い場合は別の計算法で数値が上がったとしても、安全だと判断されるとは限らないのではないか」
さらに、同じ新聞の第二面にも関連記事があり、ある大手のデベロッパーが、建設中の二棟のマンションを「偽装もなく、耐震強度も基準を満たしているが、設計の配慮不足 が見つかった」という理由で建設・販売を中止した事実が報じられています。その建物は両方とも「限界耐力計算法」で計算されていた、とのことです。注)
注)
「設計の配慮不足」の詳細な内容は明らかにされていないので勝手な推測に過ぎませんが、おそらく、限界耐力計算法で設計された建物の耐震強度を「従来の計算法」で再検証したら強度が足りなかった、ということなのではないでしょうか。
前回のコラム「震度 5 強で倒壊のおそれあり?」の最後に、「建築基準法にしたがって設計されているのに耐震強度の指数が 1 を下回る、というようなケースだってありうるはず」という話をしました。
その時念頭にあったのは、「保有水平耐力の検証を免除されている低層の建物」だったのですが、そうではなくて、今回の記事にあるような「新しい、高度な(とされている)設計法が用いられた中層の建物」についてもそういうことが起こりうることが分かったわけです。注)
注)
もっとも、このことは一部の専門家の間では前から指摘されていたことなので、べつに「今回初めて分かった、驚いた」ということではありませんが。
余談ですが、先の記事を目にしたある人(非-建築関係者)から、「それだったら、某建築士も、最初からその限界耐力計算とやらを使っていれば、誰からも偽装と言われず、こんな騒ぎにもならなかったのではないか」と言われました。
国土交通省が公表している耐震強度の指数というのは、1981 年に制定された新耐震設計法にもとづいて算出されたものです。
2000 年から使用可能になった限界耐力計算法を「新しい、高度な方法」とすれば、こちらは「ちょっと古い、簡便な方法」です。わたしたちの一般常識からすれば、「新しい、高度な方法」の方が「より精緻で正しい」はずですから、それで耐震強度 0.85 から 1 に上がったのであれば、「いろいろあったが結果オーライ」ということで何となく収まりそうなものですが、それがそうなっていないのは、この記事の内容からも明らかです。
「古い設計法」が淘汰されて「新しい設計法」に塗り替わったのならべつに問題はありません。どの世界でも「よくあること」です。
しかし、現在の建築基準法では「どちらを使ってもよい」「両方あり」とされています。つまり、その最初の意図がどうであれ、結果としては「ダブルスタンダード」になっている(あるいは「そのように見える」)わけですが、この状況が今回の記事のような混乱を引き起こしたことは間違いありません。注)
注)
「ダブル」どころか、 2005 年からは「トリプル」になっているのですが、これについては次項に述べます。
「震度 5 強で倒壊のおそれあり?」(以下「前回のコラム」と呼びます)では、この「新しい設計法」についてはまったくふれませんでした。
この新聞記事には、限界耐力計算法について、「建物の変形の影響を考える計算法で、どこまでの変形を許容するかという設計者の裁量が結果に大きな影響を与える」という内容の簡単な紹介がありましたが、ほとんどの方は、そう言われても「いったい何のこと?」と思うはずです。そこで、勝手に気を回し、(頼まれもしないのに)前回の続編を書くことにしたわけです。
1. 限界耐力計算の登場
前回のコラムで、1981 年施行の「新耐震設計法」の登場までを簡単に跡付けましたが、その要旨は以下のようなものです。
-
1981 年までは、建物の耐震設計は「中規模の地震(震度 5 程度)にたいして損傷しない」ということを目標にして行われてきた。それを超えるような規模の地震(震度 6 あるいは 7 )にたいする検討は特に行わなかったが、しかしそれまでの被災経験から「計算外の余力」によって倒壊までには至らないことが実証されていた。
-
しかし、建物の倒壊までを追跡するための技術的な手法が確立されたので、1981 年になり、「計算外の余力」に頼るのではなく、「建物の倒壊までをちゃんと検証しよう」ということになった。これが「保有水平耐力の検証」である。
-
ただし、1981 年以降も、低層の建物でかつ一定の条件をみたすものについては保有水平耐力の検証を省略し、「計算外の余力」にたよってもよい、とされている。
ところで、1981 年以前も以後も、超高層ビル(高さが 60 メートルを超えるもの)に対しては、上に述べたこととは関係なく「特別な検証方法」が別途採用されており、複数の専門家による「特別な審査」が行われています。これが「高層建築物の大臣認定」制度で、通常の建築物の確認申請とは異なるシステムになっています。
ここで採用される設計法は「時刻歴応答解析」(あるいは単に「応答解析」「振動解析」)と呼ばれています。
前回も述べたとおり、地震の力(地動加速度)というのは時々刻々変化し、しかも一方的にある方向に作用するのではなく、方向を変えながら繰り返し作用します。
時刻歴応答解析というのは、その名前が示すとおり、「時間によって変化する地動加速度を建物にそのまま作用させ、その挙動を各時刻ごとに逐一追跡して検証する」方法です。と言っても、べつに模型を作って揺らしてみるわけではなく、コンピュータ上のシミュレーションを行うのですが、これが今のところ、「地震によって建物が揺すられている」という状況の最も忠実なモデル化であるとされています。
ならば、そのような手法を超高層ビルだけでなくすべての建物に採用したらいいではないか、と思われるかもしれませんが、それがなかなか簡単には行きません。
ことの性格上、法制度化になじまない部分があるという技術的な問題と、あとは「人」の問題です。つまり、そのような解析を適切に行うためには設計者の側にかなり高度な専門的知識と経験が要求されること、さらには「それを適正に審査できる人がどれくらいいるのか」ということです。
そこで、
時刻歴応答解析のような高度で複雑な方法によらず、その結果を何かもっと簡便な方法で大づかみに推定する方法はないものか
という話になりました。
そして、そのような流れの中で 1981 年の新耐震設計法の「保有水平耐力の検証」という手法が公表 注) され、さらに遅れて 2000 年の「限界耐力計算法」、2005年の「エネルギー法」がつづくことになったのです。
注)
「公表される」というのは何なのかというと、国土交通省の告示というものが出て、その中に詳細な計算式が書かれていて、「以後、この方法で計算してもよろしい、建築基準法に則った構造計算と認めます」という状態になる、ということです。
このうちの 2000 年の「限界耐力計算法」というものが今取りざたされているわけですが、これは新耐震設計法から 20 年の時を経ているだけあって、「最新の知見にもとづいた、より高度な計算方法」、つまり「時刻歴応答解析により近い値を与える方法」として位置づけられています。また、2005 年の「エネルギー法」もこれとほぼ同レベルのものと考えておけばいいでしょう。注)
注)
「エネルギー法」に関する告示は 2005 年 9 月に施行されているのですが、まだ日が浅いこと、およびこれにもとづいた市販のコンピュータプログラムがないこと、等の理由から、今のところほとんど使われてません。
幸か不幸か、その直後の 2005 年 11 月に「耐震偽装事件」が起きたために、「エネルギー法どころではなくなった」というのがこの業界の現状かもしれません。実際、わたしの周辺の技術者に何人か聞いてみたところ、ほとんどの人が「そういうものがあるのは知ってるが内容はよく知らない」と答えました(もちろん、わたしもよく知りません)。したがって、ここでもただ名前をあげるだけにとどめておきます。
ここまで述べてきた計算手法を「簡便な(とされている)ものから高度な(とされている)ものへ」の順番で並べてみると下のようになります。
2. 限界耐力計算の「その後」
限界耐力計算法は 2000 年施行の改定建築基準法の中に含まれているものです。この法律は「規制緩和」「市場の開放」を目的とする「性能規定化」を看板に掲げていましたから、限界耐力計算法は「建築構造の性能設計を実現するためのツール」として脚光を浴びたわけです。
しかし、実際には・・・というような話はすでに「限界耐力計算ってなんだろう?」の中でふれましたので省略しますが、ようするに、結果としては、
許容応力度等計算 = 従来の(新耐震設計法による)設計法 = 仕様型設計
限界耐力計算 = 新しい設計法 = 性能型設計を実現するもの
という「二本立て」の構図におさまり、「両方あり」となりました。
で、その後にどういうことが起きたかというと、さかんに言われたのは
許容応力度等計算と限界耐力計算、いったいどちらを使ったら経済的か?
という話で、わたしもあちこちで「試算表」というものを目にしました。
そこには、「限界耐力計算を使えば一般に経済設計が可能だが、建物の規模によってはそうでないこともあるので注意」、あるいは「剛性率や偏心率が収まらない建物では限界耐力計算を使った方が有利」というようなことが書かれていたと記憶しています。
これは「性能設計ツールとしての限界耐力計算法」という本来の趣旨からはずいぶん外れているような気もしますが、しかし「どちらでもいい」と言われ、かつどちらかを使うことによる格別のメリットが見出せない(実際そうだったのですが)のならば、誰でも「より安い方」を選びたくなります。ヤマダ電機とヨドバシカメラが軒を並べていたら、たいていの人は両方の店の値札を比べてより安い方を買うはずです。誰もその人を「意識が低い」と非難したりはしません。
その後、2002 年になると限界耐力計算法による構造計算プログラムに大臣認定というお墨付きがおりるようになり、確認申請上も「普通の構造計算」として取り扱われるようになると、限界耐力計算法の使用頻度はぐんと増加しました(統計的にどれくらいの比率になるのかは資料がないので分かりませんが)。
そして、それにつれて「どちらが経済的か?」という論議は影をひそめたように思います。これは、そういうコスト認識がすっかり定着したためなのか、あるいは社会状況の変化によって、単純なコスト比較とは別に「性能設計によるメリット」が享受できるようになったからなのでしょうか?
もし後者の理由であれば、限界耐力計算法がその本来の機能を発揮しはじめた、ということになるのですが、さあ、そのあたりはよく分かりません。
しかし、この状況は今般の耐震偽装事件をきっかけ一変しました。端的な言い方をすると、
限界耐力計算法というのは、どうも今ひとつ信用できない
という風潮になってきたのです。
冒頭に紹介した報道にあるような、限界耐力計算法で設計されたマンションにたいして「耐震性に対する配慮に欠ける」という理由で建築・販売を中止する、というような事例が出てきました。また、一部の確認審査機関では、「限界耐力計算法を使用したものについては事前通知・予備審査を義務づける」としており、このような取り扱いは今後全国的に波及しそうな勢いです。
こうなってくると、
限界耐力計算法の構造計算書を確認申請に出したら「従来の方法で再検証してくれ」とつき返された
ということだって十分に起こりそうです(いや、すでにあるのかもしれません)。
こういう状況になると、多大なリスクを背負ってまでこの「限界耐力計算包囲網」を突破しようとする人は、これからどれくらい出てくるだろうか、という余計な心配までしたくなってきます。
いったい、性能設計ツールとしての限界耐力計算法 はどこに行ってしまったんでしょう?
3. 限界耐力計算と「耐震基準」の関係
そもそも、限界耐力計算法は 2000 年に制定された 新しい耐震基準 なのでしょうか?
もしこれが「新しい耐震基準」と呼ぶべきものであるのならば、法律上は古い基準と新しい基準の「二本立て」なのですから、これはまぎれもない「ダブルスタンダード」です。注)
注)
「ダブルスタンダード」という言葉はふつうは批判的な意味をこめて使われますが、じつは、わたしたちはこれまで「ダブルスタンダード」を結構上手に使いこなしてきているのです。ようするに「神仏習合」です。
早い話、現在の建築構造計算の細則については、国土交通省(あるいは日本建築センター)系の規定と日本建築学会系の規定の「ダブルスタンダード」になっています。その証拠に、たいていの構造計算プログラムには「国土交通省系の式を使うか、それとも日本建築学会系の式を使うか(神式にするか仏式にするか)」というオプションが随所に設けられていて、それがちゃんと「大臣認定プログラム」として通用しています。
そして、構造設計者は時と場合に応じてそれらを巧みに使い分けていますし、それが特別に問題視されることもありません。
でも、世間一般には、「現在の日本の耐震基準はダブルスタンダードになっている」という認識はないと思われます。
「耐震改修」「耐震補強」ということが最近さかんに言われます。「耐震改修促進法」という法律だってあります。
これはようするに、「古い耐震基準で建てられた建物は耐震性に問題があるので補強しましょう」ということですが、ここでいう「古い耐震基準」とは「 1981 年に制定された新耐震設計法より前の基準」のことを指します。そして、この基準の正当さが 1995 年の阪神淡路大震災によってほぼ証明されたので、この基準にしたがっていれば、阪神淡路大震災クラスの地震がきても建物に大きな被害はでないであろう、という経験知にもとづいて「補強」「改修」がしきりに叫ばれているのです。
ここから何が分かるのかというと、
日本の耐震基準は 1981 年に改定されたが、その後は一度も改定されていない(少なくとも改定されたという一般認識はない)
という事実が分かります。
となると、「 2000 年の改定建築基準法とは何だったのか」です。
もし、改定基準法が現行のような「二本立て」でなく、たとえば限界耐力計算なり時刻歴応答解析なりに「一本化」されていた場合を想定してみます。おそらくこの場合は、明確に「日本の耐震基準は 2000 年に変わった」と言われたことでしょう。
でも、そうではなかったし、そう言われてもいません。だからやっぱり「耐震基準は変わっていない」のです。
現在の耐震基準の骨子となっている考え方は、前回も述べたとおり
建物の耐用年数内に一度以上は遭遇すると思われる中規模の地震(震度 5 程度)にたいして損傷を受けないようにし、さらに、建物が遭遇するかもしれない最大級の地震(震度 6 から 7 )にたいして人命の安全を確保する
というものです。
たしかに、このスタンスは 1981 年以来揺らいでいません。「耐震基準は変わらなかった」とする根拠をもとめようとするなら、それはここにしかないはずです。
こういう立場に立てば、
国の耐震基準 1981 年以来変わっておらず、「ダブルスタンダード」など存在しない
と言うことができそうです。
では、 2000 年にいったい何が変わったのか?
「基準にさだめる耐震性能を検証するためのあらたな手段が提供された」のです。
ここに「耐震性能」という山があります。頂上に看板が立っていて、そこに「中規模の地震で損傷せず、大規模の地震で倒壊しない」と大書されています。
この山の北面は切り立った崖ですが、それなりの装備で、かつそれなりの訓練をしている人なら登って行くことができます。一方、南面にはだらだらした登り坂の山道があり、こちらなら軽装で休み休み登っていくこともできそうです。
この山の麓で、建築基準法は、登山者にたいし、「どちらのルートをとってもいいですよ、最終的に行き着く場所は同じですから」と言っているわけです。
でも、本当はそんなに単純ではありません。これは数学の証明とは違うからです。
たとえぱ「ピタゴラスの定理」というものがあって、それを証明する方法は(有名なもの無名なものを含めれば)ほとんど無数にあります。そのどれを使っても、「直角三角形の二辺の長さの二乗の和は長辺の長さの二乗にひとしい」ことが証明できます。どのルートを使って登ってもちゃんと頂上の旗に行き着くのです。
しかし、人間の顔がそれぞれ異なるように建物は一つ一つ何がしか異なり、また異なる条件にさらされています。ましてその「耐震性能」ということになれば、相手が自然現象ですから、これを単純明快な式であらわすことなど不可能です。せいぜいできるのは、「 A と比べれば安全だが、B と比べたら少し危険」というような相対的な評価だけです。
結局、どうやったところで、法にさだめる「安全」というのは、全体を大づかみにとらえた 最大公約数的な安全 にしかなりません(もちろん「それ以上」を望むことはできますが、それなりのコストを覚悟しなければなりません)。
つまり、先ほどの比喩を使うならば、「頂上に旗など立っていない」のです。旗を立てるべきピンポイント、「絶対的な安全」というものがないからですが、しかしこれでは、何を手がかりに山を登ったらいいのか分からなくなってしまいます。そこで、国の行政は、このあたりまできたら「山に登った」と見なします、という所に線を引くことにしました。
これが「法に定める最低限の耐震性能」です。さらに上を目指したい人はどんどん登って行ってもいいですが、しかし「最低限ここまでは登ってきてください」というわけです。
山登りの比喩をさらに続けることにします。
山の北面は急峻な崖で、南面はだらだらした登り坂です。このだらだら坂の方を従来の設計法 注)、急峻な崖の方を 2000 年施行の新しい設計法(限界耐力計算法)にたとえることができます。
注)
ここまで、「新耐震設計法」「保有水平耐力の計算」「従来の計算法」というさまざまな呼び方をしてきましたが、みな同じものを指していますので、以後は「従来の計算法」で通すことにします。
だらだら坂の方は、なにしろこれまで 20 年以上も使われてきたものなので、いろんな人の足跡がいっぱいついて、しっかり踏み固められています。自分自身が何度も来ている道なので、迷う心配もありませんし、その上、あちこちに道標が立っています(うっとうしいくらいに)。竹薮をかき分けてクマでも出てこないかぎり、何の心配もいりません。
これに対し、北面の崖をいさんで登りだした人は大変です。なにしろあまり人が通ったことがないので、どの岩を手かがかりにしてどういう順番で登ったらいいのかがよく分かりません。何よりも困るのは、「どのあたりまで登ればいいのか」がよく分からないことです。
もし、同じルートをたどった人がたくさんいたり、あるいは近くに熟練者がいれば助言をもとめることもできるのですが、それもありません。そこでポケットから岩登りのマニュアルを出して読んでみると、「どこまで行くかはあなたの裁量しだい」と書いてあるので、あまり自信はないけれども「そのあたりでいいか」ということにします。
ここで、山の北面と南面を同時に見渡せるような場所にある人が立っていて、二人を見比べ、「北面を登った人は南面を登った人よりもだいぶ低い場所にいる。おかしいんじゃないのか?」と声を上げている。
・・・冒頭の新聞記事にある状況というのは、こんな図柄であらわすことができるかと思います。
さて、「岩登り」の人はそう詰問されて大いに困惑し、理不尽さを感じます。
なぜなら、ここで「どこまで登るべきか」の判断に使われているのは「だらだら坂」の方のモノサシで、「岩登り」の人にはそのモノサシは最初から与えられていないのです。だから「だらだら坂」の人がどこまで登ったかなど分かりようがありません。
そこで「岩登り」の人はポケットからごそごそとモノサシを取り出し、「これじゃいけないのか」と言いますが、そのモノサシをよく調べてみると、けっこう「伸縮自在」に出来ていたりします。
で、どうなるのかというと、そのモノサシ自体に問題があるのではないか という話になってくるのです。
4. 限界耐力計算の問題点
限界耐力計算は「性能設計のためのツール」として登場しました。
この「性能設計」とは何なのかというと、「消費者(多くの場合は建築主)の要望に的確に応えることのできる設計」です。では、なぜこれが「性能設計のためのツール」で、従来の設計法とどのように違うのか、というと、それは
限界耐力計算では、地震力の大きさを「加速度」で評価できるようになった
ということです。これが最大のポイントだと、わたしは考えています。
これは前回のコラムで言いましたが、従来の設計法では、地震力の大きさを「建物の総重量の何パーセントの力が地震力として作用した」ととらえます。ここには「地震の加速度」という表現が表立ってあらわれてくることはありません。それは見えないところに隠されており、その結果、
どれくらいの大きさの地震をターゲットにして建物が設計されているのかがよく分からない
という不満が出てくることになります。
これに対し、限界耐力計算では「地動の加速度」「建物の応答加速度」という考え方をはっきりと前面に出してきます。だから、建築主からの「これこれの規模の地震にたいして安全に設計してくれ」という要望により的確に対処できるようになるのです。
前項で、法律にさだめる耐震性能とは「大づかみにとらえた最大公約数的な安全」である、と言いましたが、限界耐力計算では、上のような理由により、これを、より「ピンポイント」に近づけることができます。限界耐力計算という武器には「照準器」がついているのです。
さて、地震に対する建物の安全性のあらわし方ですが、最終的には両者とも同じような形になります。つまり、
保有水平耐力 / 必要保有水平耐力(応答値)
で、これが何かと取りざたされている「耐震強度(の指数)」です。
限界耐力計算では分母を「必要保有水平耐力」ではなく「応答値」と呼びます。ですが、従来の設計法でいう「必要保有水平耐力」とは、結局、「大地震がきた時に建物に生じる力」つまり「応答値」に他なりませんから、これはただ呼び方が変わっただけです。
分子になる「保有水平耐力」は両者ともまったく同じものです。これについては前回簡単にふれましたが、もう少しくわしく説明することにします。
マッチ箱(最近あまり見かけないものの一つですが)の外箱の底面を机の上に貼り付け、それを横から見たのが下図の絵です。これを「建物」と見なせば、箱の側面が柱、上面が梁または床ということになります。
この上面を手で水平方向に押して力を加えます(上図の赤い矢印)。これが建物に作用する「地震力」だと考えることにします。
マッチ箱は平行四辺形に変形しますが、力が小さいうちは手を離せば元の形にもどります(弾性状態)。さらに力を加えていくと、マッチ箱はもはや元の形にはもどらず、平行四辺形のままになってしまいます(弾性の限界を超える)。この状態でも、マッチ箱はまだ「壊れる」わけではありませんが、さらに力を加え続けるとペシャンコになります。つまり「壊れる」のですが、建物の場合はこれを「崩壊」あるいは「倒壊」と呼びます。
この場合の「壊れる」は「ペシャンコになる」ですから、いつ壊れたかは目で見ればわかります。
しかし、建築構造設計のターゲットにしているのは完成した「建物」で、それを実際に壊してみるわけではなく、コンピュータ上でそれをシミュレートするだけです。すると、ここで必要になるのは「壊れる」という状態の数値的な定義です。
そこで、マッチ箱の上面のどこかに目印をつけ、力が作用するにつれてこの点が最初の位置からどのように動いていくかという「変位量」をグラフ上にプロットすることにします。この座標軸は縦軸に力、横軸に変位をとっていますので、グラフが垂直に近く立っているほど固く(力の増加に対する変形量の増加が小さい)、横に寝ているほど柔らかい(力の増加に対する変形量の増加が大きい)という状態をあらわします。
最初のうち、つまり弾性状態にある時は作用する力に比例して変位が増加するので、このグラフは直線になります。しかし、弾性限界(上図の○印)を超えるとマッチ箱の反発力は減少し、柔らかくなります。つまり、このグラフは横に寝てきます。この状態でもまだ壊れてはいませんが、さらに力を加え続けるとグラフは一層横に寝てくることになります。これ何かといえば、「ほんのちょっとの力で大きく変形してしまう」状態です。
そこで、コンピュータ上に建物のモデルを作り、それに水平力を加えてその値を徐々に大きくしていき、床の変位を数値計算でもとめ、それをグラフ上にプロットします。そして、グラフの状態を監視しながら、それが少しずつ横に寝ていって、「ほんのちょっとの力で大きく変形してしまう」状態をつかまえたら、「このあたりで建物が倒壊するのだな」と考えるわけです。
ここで話したのはごく単純なマッチ箱の例ですが、実際の建物にはたくさんの柱があり、階数もありますから、いわば、マッチ箱を上と横につなぎあわせた下図のような状態になります。この場合は、それぞれの床の位置に力をかけて、各階ごとにさきほどのようなグラフを描きます。そして、このうちの「どこかの階」で倒壊状態になったら、その時点でこれを「建物全体の倒壊」とみなすことにしています。
耐震強度の検証式「保有水平耐力 / 必要保有水平耐力」の分子になっている「保有水平耐力」とは、この「ほんのちょっとの力で大きく変形してしまう」状態の時に作用している力のことです。これは、言い方を変えると「建物が潜在的に保有している耐力の上限値」ということになるので「保有」という言葉を使っているのです。
コンピュータによるシミュレーションで、建物のある階の力と変位の関係が下図のように得られたとします。
上のグラフの A 点にからグラフが横に寝始めています。しかし、ここで建物が壊れるわけではありません。
建物は横に大きく変形しますが、その変形に建物が追従できる限りはまだまだ壊れません。 B 点でもまだ変形に追従できるのであれば C 点まで行き、それでもまだ追従できるのなら、その先のどこかで壊れることになります。
「変形に追従でずに建物が壊れる」とは何なのかというと、分かりやすく言えば、「柱がグシャグシャになって床が落ちてくる」ような状態 注) ですが、しかしそこまでいかなくても、たとえば天井などの仕上げ材が大変形に耐えられずに落ちてくるというような状況になれば、それはまさしく「人命の安全」にかかわるわけですから、その時点で「建物が倒壊した」と見なすべきでしょう。
このように、「どこを建物の倒壊と見なすか」「どれくらいまでの変形を許すか」というのは、たんに柱や壁などの構造材がどこまで変形に追従できるか、ということだけでなく、「建物全体としての安全性」という観点を含めれば、かなりデリケートな問題になってくると言えます。
注)
さきほどは話を分かりやすくするために「ペシャンコ」という表現を使いましたが、ふつう、建物には多くの柱や壁があって複雑に荷重を支えあいますから、文字通りの「ペシャンコ状態」にはならないものです。
ところで、ここまでの話はグラフをもっぱら「変位」の側から見た場合のものですが、一方、これを「力」の側から見てみるとどうでしょうか?
上図の点 A・B・C に対応する力は、この点に水平線を引いて縦軸との交点を読み取れば分かります(それがすなわち「保有水平耐力」です)が、ここから分かるように、その値はほとんど変わりません。なぜなら、この領域は「ほんのちょっとの力で大きく変形してしまう」のですから、 A・B・C のどれをとっても、それらの力の差は「ほんのちょっと」しかないのです。
このように、「どこを建物の倒壊と見なすか」というデリケートな判断は、「保有水平耐力」の値にはさほど影響を与えません。そして、従来の計算であれ限界耐力計算であれ、これに関してはまったく同じです。
ではいったい何が違うのか、何が問題になるのかというと、それは、さきほどの式の分母の方、つまり「必要保有水平耐力(あるいは応答値)」です。
ここまでの話を聞いて、あるいは、
建物が A 点に到達して、潜在的に保有する耐力をほぼ使い切ってしまった。しかしその後も地震力が作用し続けて B 点 あるいは C 点にまで行くという。では、 A 点に到達後に作用する地震力はいったい どこに行ってしまう のか?
A 点が建物の耐力ならば、それ以上の地震力には耐え切れず、この時点で建物が壊れてしまうのではないか?
という疑問を持たれるかもしれません。
じつは、 A 点を過ぎると、建物は地震力に「抵抗する(耐える)」のではなく、今度は地震力を「吸収」し始めるのです。そして、なぜそんな芸当ができるのかというと、それは、このグラフが横に寝てくることによって建物が「柔らかく」なるからです。
白木の板を気合もろとも拳骨で壊すことはできても、ゴムの板を壊すのはなかなか大変です。ゴムの板は柔らかいのでそれなりに「変形」し、変形することによってパンチ力を「吸収」するからです。この機構により、結果的にパンチ力は「減殺」されます。これを「エネルギーの吸収機構」と呼んだりします。注)
注)
「エネルギーとは何なのか?」という話は長くなるので省きます。ようするに、日常会話で使うような意味合いのものだと漠然と理解しておいてください。
「制震構造」という言葉をどこかで耳にしたことがあるかもしれません。
これは、建物の骨組の中に「ダンパー」と呼ばれる可塑性のものを取り付け、ここで地震のエネルギーを吸収して建物の自体の揺れを少なくする、という考えに立った建築物です。ここで話していることは、いわば、建物そのものが柔らかくなって「ダンパー状態」になる、ということです。
ですから、たとえば 10 のエネルギーに相当する地震力が建物に作用したとしても、その半分のエネルギーを建物が吸収してしまうとすれば、
地震のエネルギー 10 = 建物に吸収される分 5 + 建物に力として作用する分 5
という等式が成り立つことになります。つまり、実際には 10 のエネルギーに相当する力が建物に作用しているにもかかわらず、見かけ上は半分の 5 に相当する力しか建物に作用していないように見えるのです。建物のエネルギー吸収能力が 7 に相当すれば、建物に作用する分は 3 に減ります。
ここにいう「地震のエネルギーのうちの建物に力として作用する分」が建物を揺らすわけですから、これが地震力に対する建物の「応答値」になります。つまり、これが耐震強度の検証式「保有水平耐力 / 必要保有水平耐力(応答値)」の分母です。
さて、これで耐震強度の検証式の分子についても分母についてもその意味は分かりました。分子の値のもとめ方はすでに言いました。
残るは「分母の値のもとめ方」です。
さきほど言ったとおり、この分母の値とは、大地震時に建物に作用するエネルギーから建物が吸収できるエネルギーを差し引いたものですから、建物のエネルギー吸収能力が大きいほどこの値は小さくなります。
この値をもとめるということは、ようは、「建物のエネルギー吸収能力がどれほどのものか」を見積もることです。ここで、「建物のエネルギー吸収能力が高い」とは、建物を構成する柱や壁などの部材が「大きな変形に壊れずについていける」ことを意味します(これをよく「粘りがある」などと言います)。
従来の計算法では、この値(建物のエネルギー吸収能力)をもとめるための手順がすべてマニュアル化されています。
簡単に言うと、まず、柱などの部材にどのようなサイズのものが使われているか、などのデータをもとに一つ一つをランク付けします(変形能力が高いものが A ランクとされ、以下、D ランクまで存在します)。その部材を集計し、たとえば A ランクの部材が全体の何パーセントを占めているか、というような数値をもとに表を引いて建物のエネルギー吸収能力を決めます。ようするに、「源泉徴収税額表」を使って給与の額と扶養家族の数から税額を決めるみたいなものです。
この方法の利点は何かというと、マニュアルにしたがって作業すればいいので、設計者による「まぎれ」がなく「誰がやっても同じになる」ことです。
欠点は何かというと、建物のエネルギー吸収能力というかなりデリケートで複雑なものをマニュアル化のためにあえて単純化しているので、そこから得られる値には「まあこんなもの」というアバウトさがつきまとうことです。
これにたいして限界耐力計算はどうかというと、これは、より「ピンポイント」であることを目指しますから、そんなアバウトなことはしません。
じつは、建物がどれくらいエネルギーを吸収したかというのは、さきほどの「力-変位」のグラフを見れば分かることになっています。その吸収量は、このグラフと変位量をあらわす横軸が囲む面積に等しくなります。注)
注)
これについても、なぜそうなのか、という話は長くなるので省略しますが、さきほどのゴム板の話を思い出していただければ、これは「変形が大きいほどエネルギーの吸収量は大きいはず」という経験的な判断と一致することは分かるかと思います。
つまり、下図において変位量が C 点まで達したなら、ここまでのエネルギー吸収量は黄色く塗りつぶした面積によってあらわされる、ということです。
限界耐力計算ではこの考え方をそのまま使います。
上の図から分かるように、 B 点で建物が壊れるとした場合よりも C 点で壊れるとした場合の方が建物のエネルギー吸収量は大きくなります。エネルギー吸収量が大きくなれば、その分だけ建物に作用する力が減ります。つまり「応答値」、耐震強度の検証式の分母の値が小さくなり、結果として耐震強度の安全性をあらわす指数は大きくなるのです。
となると、
では、建物が変形に耐えられる限界点( B 点なのか C 点なのか)はどのようにして決めるのか?
という話に当然なってきますが、これについては、
基本的に、設計者が自分の裁量で決める
ことになっているのです。
そして、限界耐力計算法の問題点としてしきりに言われるのが、他でもない、このことなのです。
建物の変形の限界点を B 点とするか C 点とするか、というのはいかにも「ピンポイント」を旨とする限界耐力計算法にふさわしい発想のようにも見えます。しかしここには、「そのピンポイントが正当なものであるのならば」という前提があります。さきほど、「限界耐力計算法という武器には照準器がついている」と言いましたが、いくら優秀な照準器がついていても、ウサギと間違えて人を撃ってしまっては何もなりません。
さきほどの図から明らかなように、限界点を B 点とするか C 点とするかによって耐震強度の評価は大きく動きます。しかし、建物の変形の限界とはどのあたりなのか、という点についての一致した見解あるいは考え方というものは今のところありません。また、制度としての限界耐力計算法の中に、とくにこの値にかんする上限が設けられているわけでもありません。
ということは、極端な場合、「設計者のサジ加減によって耐震強度を恣意的に増減させる」ことさえ出来てしまうのです。前項のたとえ話の中で「伸縮自在のモノサシ」と表現したのはこのことです。注)
注)
かと言って、設計者がまったくデタラメにこの値を決めているのかというと、もちろん、そういうことではありません。
とにかく設計者が最初に任意の限界点を決めること、それは間違いありませんが、コンピュータ上のシミュレーションによって、「その値に達した時の建物の状態」を再現することができます。そして、その状態において個々の柱や壁がおのおのの限界を超えるような過大な変形を被っていないことを確認し、それが確認されれば「最初に仮定した限界値は正しかった」として設計を終える、というのが一般的な設計の手順です。
しかし、この検証方法についても、とくに具体的な手法が制度として定められているわけではなく、実際には、「なんとなくみんながそうしている慣用的な手法」を採用することになります。
そういう意味では、やっぱり「伸縮自在のモノサシ」であることに変わりはないといえます。
5. 限界耐力計算の信用
従来の計算法と限界耐力計算法で同じ建物の耐震強度を計算した場合、その値が同じにはならない、少なくとも同じになる保証はどこにもない、というのは、ここまでの話からなんとなく理解していただけたのではないかと思います。
同じにならない理由は、まず何よりも使っているモノサシが違うからです。そして二つのモノサシの対応関係がよく分からないこと、さらに、片方のモノサシが「伸縮自在」なことです。これについてはすでに言いました。
建物の耐震性能にかんする「絶対的な評価」というものはありえません。その建物に対してどの向きにどのような大きさの地震がくるかは誰にも分からないからです。
たとえば、人の「身長」なら誰が測っても同じになりますが、人の「性格」はそうは行きません。評価する人とされる人の関係、あるいは評価する本人の性格も関与してきますから、その人の性格をたった一つのモノサシで断定的に決めつけるわけにはいきません。つまり何を言いたいのかというと、建物の耐震性能とは、「身長」てはなく「性格」に近いものだろう、ということです。
であれば、異なる二つの見解が差し出された時、問題は「どちらが より正しいか」ではなく、「どちらを より信じるか」ということになります。そして現在、この点にかんして、限界耐力計算法の方が圧倒的に分が悪いことはここまで述べてきたとおりです。
なかなか信用されない最大の理由は、従来の計算法が 20 年以上も使われつづけ、しかもその間に阪神淡路大震災という超ド級の試練を潜り抜けてきたのに、限界耐力計算法にはそのような「経験の集積」がない、という点にあるでしょう(限界耐力計算法の側にしてみれば、それを言われたらミもフタもない、ということにになりますが)。
信用されないもう一つの理由は、何度も言ってきた「伸縮自在のモノサシ」です。そのモノサシの正当性を証明する手立てが限界耐力計算法の中に制度として定められているわけではないので、設計者は、それを自力で行ない、かつ納得のいく説得をしなければならないという困難があります。
限界耐力計算法は、従来の計算法の「アバウト」から脱皮して「ピンポイント」を目指すための武器として誕生しました。ですから、限界耐力計算法で設計された建物を従来のモノサシで測りなおして「強度が足りない」というのは、本来の理屈からいえばアベコベなはずです。
となると、では、限界耐力計算法は どういう場合にどの程度まで信用していいのか という話になってきますが、もちろん、そんなことは分かりません、わたしには。せいぜい言えるのは 信頼できる技術者がやっているのなら信頼していいのではないか ということぐらいです。
これは何もわたしが言っているのではなく、(新聞報道によれば)総元締めの国土交通省が言っているのです。冒頭に引用した国土交通省のコメントを再度掲げておきます。
「計算結果が食い違う場合こそ、安全性を判断するためには専門家の助言が必要になるだろう。ただ、元の強度が著しく低い場合は別の計算法で数値が上がったとしても、安全だと判断されるとは限らないのではないか」
というわけで、ここまでいろいろと書いてきましたが、最後の結論は「よく考えてみればアタリマエの話」で終わってしまいました(たぶんそうなるだろう、ということは最初から予想していたのですが)。
(終わり)