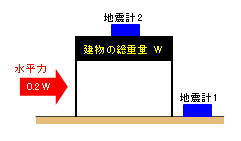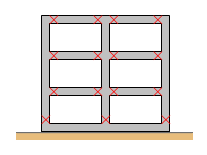震度 5 強で倒壊の恐れあり?
先日、構造設計に携わっている方と話をする機会があり、話題は自然と今回の「構造計算書偽造事件」に及びました。といっても、事件そのものではなく、国土交通省が発表している「建物の耐震強度をあらわす指数」というものについてで、「あれはいったいどうやって算出したものなのか?」という疑問です。
そこで、国土交通省が公表している資料をのぞいてみると、この指数は「Qu/Qun (最小値)」という形であらわされていることが分かりました。
構造計算の一般的な常識から考えると、この Qu は「建物の各階の保有水平耐力」、Qun は「建物の各階の必要保有水平耐力」でしょうから、だとすると、これは「各階の保有水平耐力と必要保有水平耐力の比をとり、その最小値を建物の耐震強度の指数とした」ということだと推測されます。注)
注)
地震時に建物に作用する力は、それを「横に揺らす」ように作用しますので、水平力(水平方向の力)と呼ばれます。「保有水平耐力」とは、この時に「建物がどの程度の水平力まで耐えられるか」をあらわします。つまり、これは「建物が潜在的に保有している耐力」です。
これに対して、「必要保有水平耐力」とは「最低これだけの耐力が必要である」とされる耐力の下限値をあらわします。いったい誰がそれを「必要」としているのかというと、直接的には「そこに住んでいる人」ということになりますが、それを社会制度として保証しているのが建築基準法をはじめとする法令です。
この「必要保有水平耐力」とは、工学的に見れば、「起こりうる大地震の時に建物に作用する水平力」ということになります。法令は、「大地震の時にはこれくらいの水平力( = 必要保有水平耐力)が建物に作用する可能性があるから、それに耐えられるように設計しておきなさい」と言ってるわけです。
それはそれで十分に納得できたのですが、注目すべきは、そこに「(この値が)おおむね 0.5 以下の場合、震度 5 強で倒壊の恐れがある」とコメントされていることです。実際、この「震度 5 強で倒壊の恐れがある」という言い回しは、その後各種の報道で頻繁に引用されました。
ところで、そうなると、
では、建築基準法どおりに設計した場合、つまりこの指数が 1 の場合、その建物は震度いくつまで耐えられるのか?
という別の疑問だって湧いてきます。実際、その質問をわたしは別の人から受け、それがこのようなコラムを書くきっかけになったのですが、建築構造に関わる仕事をしておられる方なら、(とくに最近は)何度か同じような質問を受けた経験があるかもしれません。
この質問に対する当面の答えは、
はっきりしないが、震度 6 から 7 ぐらい
というものです(たぶん)。
建築基準法およびそれに関連する法令(以下、たんに「法令」といいます)に「建物に作用する地震力に対して安全に設計すること」とは書かれていますが、「その地震力とは震度(正確には震度階)にするとどれくらいのものなのか」については何も書かれていません。
そもそも震度階(以下、この表現を使用します)というものは、地震のもたらす体感や被害状況に応じて定められた「相対的な評価」で、建物に及ぼされる「力」という「具体的な数値」にそのまま置き換えられるものではないからです。「震度 6 と言ったっていろいろある」のです。
したがって、良心的な技術者であればあるほど、「震度いくつまで耐えられるのか」という質問に対しては、「はっきりしないが」という前置きをつけざるを得ないことになります。
しかし、にもかかわらず、国土交通省は今回、「震度 5 強で・・・」という表現をあえて選択し、それが世の中に広く流布しました。このことの意味は、建築構造の仕事に携わる人間にとって決して小さくはありません。
なぜそんなことが言えるのかというと、この「震度 5 強で・・・」という表現を見聞きした時、わたしは「もしかすると、これが性能設計というものなのかもしれないなあ」と考えてしまったからです。これはあながち突飛な感想ではないはずです(もしかすると突飛かもしれませんけど)。
2000年施行の改定建築基準法の目玉は「性能設計」でしたが、建物の耐震性に関して言えば、「これこれの大きさの地震に耐えられる建物にしてくれ、という消費者の要求に的確に応じること」が「性能設計」の基本コンセプトです。
そして、これをひっくり返すと、「この建物がどのような耐震性能をもっているのか、という消費者の質問に、的確に、かつ分かりやすく答えること」となります。これが性能評価の基本コンセプトです。だとすれば、国土交通省が今回行ったことは、まさしく「性能評価」なのです。
そして、消費者に「地震の大きさを分かりやすく伝える」ことのできる最も手近なタームといったら、(少なくとも今のところ)それは「震度階」を措いて他にありません。
というわけで、もともと「はっきりしないもの」であることはうすうす承知しながらも、震度階と法令(耐震基準)の関係について一通りおさえた上で「震度 5 強で倒壊の恐れあり」というコメントの意味を探ろう、というのがこのコラムの目的になります。
1. 震度階と加速度
震度階とは、気象庁が発表している、地震の大きさの程度(どれぐらい揺れたか)をあらわす指標値です。
先に、震度階とは「はっきりしないもの」であると言いましたが、ある時期までは、この値は「棚の物が落ちる」「立っていられない」等の状況によって決められるまったくの「印象批評」でした。
しかし、1996 年(阪神淡路大震災の翌年)に計測震度計により自動的に観測するシステムに切り替わり、同時に、従来の震度階( 0 から 7 までの 8 段階)に「5弱」「5強」「6弱」「6強」を追加した計 10 段階の分類になりました注)。さきほど、震度階とは「相対的な評価」であると言いましたが、この時期からはある意味で「絶対的な評価」になったのだとも言えます。
注)
このあたりはすべて気象庁のウェブサイトから仕入れた知識です。余談ですが、わたしは、震度に 0 という階級があることを今回はじめて知りました。震度 0 とは「地震が起きていない」状態ではなく、「地震が起きているが誰も気づかない」状態のことらしいです。
計測震度計というものがどのようなプロセスで震度階を算出しているのか、については(気象庁のウェブサイト にありますが)わたしはよく分かりません。ただ言える事は、計測震度計を使うようになったからといって、従来の(体感その他にもとづいた)震度階の体系そのものが変わったわけではない、ということです。担当官の「印象」にたよった従来の方法では、どうしても判定に「ばらつき」が出るため、それを調整するための数値的な裏づけをもとめた、ということのようです。
ところで、わたしたち(建築構造技術者のことを指します、以下同じ)が問題にするのは、もっぱら「地震によって建物にもたらされる水平方向の力」のことです。ニュートン力学によれば「力」は「加速度」によって生じることになっていますから、この力の原因となるのは「地震によって生じた加速度」です。
そこでわたしたちは、
震度階が上がると建物の被害が増えるのは、建物に作用する「力」が増えるためである。
その力の原因となるのは「加速度」である。
だからようするに、震度階が上がると地震の加速度が大きくなるのである。
と考えます(これは正しいはず)。
となると、あとは「震度階と地震の加速度の関係」さえ分かれば、そこから「建物の耐震性能と震度階の関係」を導くことができるはずです。
・・・しかしどうやら、ことはそう簡単ではありません。
簡単でない理由の一つは、「震度階は地震の加速度だけから決められているわけではなく、震度階と加速度の間には必ずしも明確な対応関係がない」ことであり、もう一つは、「加速度は時々刻々変化する」という事実です。
震度階を計測するための機械(震度計)とは別に、地震の加速度を記録する機械(地震計)というものがあります。ここから得られるのが「地震波」と呼ばれるものですが、その一例を下にしめしておきます。
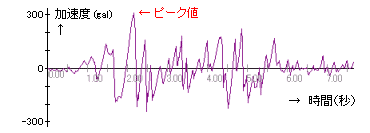
これは時間を横軸、加速度を縦軸にとったグラフですが、これを見れば「加速度が時々刻々変化する」のは一目瞭然です。しかし建物の耐震設計において、この「時々刻々変化する力」をパラメータとするのは非常に煩雑なので、(超高層建築物などを除き)通常は「変化しない、一定の力が建物に作用した状態」を考えることになります。
そして、この時の「一定の力」として何を採用するのかというと、「その地震の加速度の最大値 = 最大加速度」です(上の図に「ピーク値」と赤い字で記しています)。この力は、実際には、建物に「ほんの一瞬」作用するだけですが、その瞬間のスナップショットを捉えて設計するわけです。
ただし、この「ほんの一瞬」の力の大きさだけでその地震の規模(及ぼす被害の大きさや体感までを含めたもの)があらわせるのかというと、そうではありません。たとえば「揺れの継続時間」が被害の大きさに直結すること、あるいは「ゆっくり揺れるか・早く揺れるか」によって感じ方が違うことを、わたしたちは経験的に知っています。
それはまったくその通りなんですが、一方、建物の設計では「力 = 加速度」というものを頼りにするしかないのです。これは困ったことです。
しかし幸いなことに、「一般に、地震の規模が大きくなれば、それにつれて最大加速度も大きくなる」という経験的な事実もたしかに存在します。そこで、
大雑把でもいいから、最大加速度と地震の規模を関連づけることができないか?
という話になります。
で、調べてみると、そういうものがたしかにありました。
「河角の式」と呼ばれるもの(河角博士という方が提唱した式)がそれで、これは、最大加速度の常用対数と震度階を一次式で関連づけた非常にシンプルな式です。これによって計算すると、震度階と最大加速度の関係は下のようになります(震度 3 以下は当面の話には関係ないので、震度 4 以上について載せています)。
震度階級
最大加速度( gal ) 注)
4
25 〜 80
5弱
80 〜 140
5強
140 〜 250
6弱
250 〜 315
6強
315 〜 400
7
400 〜
注)
加速度は通常 gal(ガル)という単位であらわしますが、これは「cm/sec2」のことです。つまり、1gal とは「 1 秒間に秒速 1cm だけ速度が増加する」状態ですが、そう言われても何のことやら分かりません。そこでよく行われるのが、地球の重力加速度を基準にとることです。
地球の重力加速度は約 980gal になりますが、これを 1G(ジー)と称します。これを使うと、200gal は約 0.2G で、つまり「地球の重力加速度の約 1 / 5 の力」ということになります。
しかし、これで一件落着といかないのが厄介なところです。
そもそもこの河角の式というのは理論的に導かれたものではなく、いわゆる「実験式」ですが、この式の精度には「どうも問題がある」「そんなに単純なものじゃない」というのが、現在の一般的な「定説」になっているらしいのです。げんに、気象庁のウェブサイトにも、単純に河角の式から逆算し、各震度階級の加速度の値を求めることは出来ません、とはっきり書かれてしまっています。
では、これに代わる何かがあるのかと(もっぱらインターネットの検索サイトに頼りながら)調べてみると、国土交通省国土技術政策総合研究所という機関のウェブサイトに、「震度と最大加速度を厳密に対応させることはできないが、概ねの値として」という前書きとともに下のような表が載っていました。
震度階級
最大加速度( gal )
4
40 〜 110
5弱
110 〜 240
5強
240 〜 520
6弱
520 〜 830
6強
830 〜 1500
7
1500 〜
この値を前のものと比べると、とくに震度階の大きい部分では「あきれるほどに」違っています。
この値の違いがどこから来ているものなのかについては、わたしには分かりようもありませんが、では、これが現在の「定説」なのかというと、どうもそうではないようです。(さきほどから「よく分からない」とか「・・・のようです」ばかり連発してますが)わたしが知りえた範囲では、実際のところ、「これといった考え方はない」というのが現状のように見えます。
ただし、「震度階と最大加速度の関係」という形で世の中に広く流布しているのはどちらかといったら、それは「河角の式」による最初に掲げた表です。その点は間違いありません。そこで、以下、この表の値を(多少の留保をつけながらも)信じて先に進むことにします。
2. 震度階と耐震強度
ここからは「建物」の話になるので、再び国土交通省のウェブサイトに戻ります。
ここに「マンションの耐震性等についての Q&A」というコーナーが(今回の事件に関連して)開かれており、その中に「現在の建築基準法の耐震基準(新耐震基準)を満たしている建築物は、どの程度の地震に耐えられるのですか?」という質問に対する回答が載っています。以下の通りです。
現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和 56 年 6 月から適用されていますが、中規模の地震(震度 5 強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度 6 強から震度 7 程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。
先に述べたとおり、法令の中に「震度 X の地震に対して・・・」というような記述は一行もありません。つまり、震度 X という明確な指標を設けているわけではありません。その理由として、(前項で述べたような)震度階と加速度(つまり「建物に作用する力」)を単純に対応づけることが難しい、という事情があげられます。
しかし、にもかかわらず、国土交通省が上のような回答をしているからには、そこに何らかの「裏付け」があるはずです。それは何かといったら、
たしかに、法令の中に震度 X という明確な指標があるわけではない。しかし、過去の地震による建物の被害状況を見てみると、建物の耐震強度と震度階であらわされる地震の規模の間には一定の関係があることが分かる。
したがって、それらの既成事実を踏まえれば、法令が定める耐震強度を震度階と関係づけていうことには十分な説得力がある(はず)。
ということなのだろうと、わたしは勝手に推測します。
ちなみに、気象庁が公表している「気象庁震度階級関連解説表」というものがあり、この中に震度階と鉄筋コンクリート造建物の被害状況が関連付けて記載されていますので、その部分だけを抜粋して以下に掲載してみます。
震度階級
鉄筋コンクリート造建物
5弱
耐震性の低い建物では、壁などに亀裂が生じるものがある。
5強
耐震性の低い建物では、壁、梁、柱などに大きな亀裂が生じるものがある。耐震性の高い建物でも、壁などに亀裂が生じるものがある。
6弱
耐震性の低い建物では、壁や柱が破壊するものがある。耐震性の高い建物でも壁、梁、柱などに大きな亀裂が生じるものがある。
6強
耐震性の低い建物では、倒壊するものがある。耐震性の高い建物でも、壁、柱が破壊するものがかなりある。
7
耐震性の高い建物でも、傾いたり、大きく破壊するものがある。
上の表には「近年発生した被害地震の事例から作成したものです」という前書きがありますが、さきほどの国土交通省の回答とちゃんと合っていることが分かります。
いや、「ちゃんと合っている」という表現はおかしいですね。
べつに耐震基準が正確だから「ちゃんと合っている」わけではないのです。(何度も言いますが)現在の耐震基準に「震度 X」という指標はないのですから、あるいは、国土交通省の人が上の表を見て、「ああ、そういうことだったの」と納得して先ほどのように回答した、ということだって十分あり得るのです。
なんだか話が込み入ってきましたので、この辺で整理しておきます。
1.
建物の耐震設計は、建物に「ある一定の力」が作用している状態を想定して行われる。
2.
その「一定の力」は地震の加速度により生じるものであるが、しかし、その加速度を一義的に「震度階」と関連づけるのは、今のところ難しそうである。
3.
にもかかわらず、そのようにして設計された建物の地震による被害状況を総括的に眺め渡すと、建物の耐震強度と(震度階であらわされる)地震の規模の間に何がしかの相関がある、ということが「結果的に」言える。
この「 1 から 3 へ」という流れは必ずしも一方通行ではなく、時には 3 から 1 へとフィードバックされることもあります。つまり、「大地震の経験を経て耐震基準が見直される」ということですが、次はそのあたりのことを考えてみようと思います。注)
注)
建築構造の専門家の方にとっては、次章に述べることはほとんど「既知の情報」だと思いますので、読み飛ばしていただいていて結構です。
3. 震度階と耐震基準
前項で引用した国土交通省の回答を再び掲げます。
現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和 56 年 6 月から適用されていますが、中規模の地震(震度 5 強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度 6 強から震度 7 程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。
ここにもあるとおり、現行の耐震基準は 1981 年に定められたものです。もちろん、それまでにも耐震基準というものは存在していましたし、いくつかの大地震( 1964 年の新潟地震・ 1968 年の十勝沖地震など)の経験を踏まえて細かな改定が行われてきました。
さらにその後、 1978 年には宮城県沖地震も発生しましたが、 1981 年の改定というのは、いわば、これらの大地震の経験から得られた英知の集大成ということになります。そして、その妥当性が 1995 年の阪神淡路大震災によって「かなりの程度証明された」ということになっています(阪神淡路大震災を踏まえた細かな改定はありますが、その基本路線は変わっていません)。
さて、この回答の内容を吟味すると、現行の耐震基準には、
1. 中規模の地震(震度 5 強程度)に対してほとんど損傷を生じない
2. 大規模の地震(震度 6 強から震度 7 程度)に対しても人命に危害を及ぼすような被害を生じない
という二つのフェーズがあることが分かります。
以下、これらのフェーズごとに順を追って見て行きます。
3-1. 中規模の地震
まず最初は「中規模の地震」です。
これはどの程度のものなのかというと、「建物の耐用年数(約 50 年程度)内に一度か二度は遭遇する可能性が高い」地震であるとされています。
この地震に対して建物が「損傷しないようにする」わけですが、この「損傷しない」とは何かというと、たとえば「壁に亀裂が入ったが、別に補修しなくても耐力上は問題ない」というような状態です。注) 人間の体にたとえれば、「ケガひとつしない」あるいは「多少のケガはしたが病院に行くほどじゃない」ということになります。
注)
「損傷する」と「壊れる」というのは別です。多少の亀裂が入っても、それを(構造工学上は)「壊れた」とは言いません。このあたりは次項で説明します。
この「損傷しない」ことをどうやって確かめるのかというと、
建物に「ある一定の力」が作用した状態を仮想し、その状態で、建物を構成する骨組(柱・梁・壁など)が損傷しないことを技術的な知見にもとづいて確認する
のです。
だとすると、次は、この「ある一定の力」とはどの程度のものなのか、ということになります。
建物の重量は最終的には 1 階の柱にすべて伝わり、ここで支持されますから、「建物全体に作用する力」を見るには「建物の 1 階の柱に作用する力の合計」を見ればよいことになります。したがって、以下、(話を単純化させるために)建物全体の重量をすべて 1 階の柱の上部、つまり 2 階の床に作用させた下図のような平屋のモデルにもとづいて話を進めることにします。
この建物に地震がくると、建物は左右に揺れます。しかし、同じ地震であっても建物によって揺れ方が違う、ということは、たとえばこのモデルの柱が長い場合・短い場合というのを想定してみれば直感的に理解できるはずです。
では、なぜ揺れ方が違うのかというと、それは建物に作用する「加速度」が違うからです。
上図のように、地面の上に「地震計 1 」、建物の 2 階の床の上に「地震計 2 」があるとします。
建物が揺れている時、この二つの地震計で計測した加速度の値は一般に異なります。普通は建物で計測した加速度の方が大きくなります。つまり揺れが「増幅」されるのです。
「地震計 1 」で計測される加速度のことを地動加速度(つまり「地面の揺れ」)、「地震計 2 」で計測される加速度のことを応答加速度(つまり「建物の揺れ」)と言います。
地動加速度が「原因」で応答加速度が「結果」です。これらの間には一定の関係がありますが、建物に作用する力の大きさ( 1 階の柱に作用する力の合計)を最終的に決めるのは「応答加速度」の方です。力は質量と加速度の積ですから、作用する力は、応答加速度もしくは建物の重量に比例します。
「建物にある一定の力が作用した状態を仮想して設計する」と言いましたが、この「一定の力」とは、ここに述べた「 1 階の柱に作用する力の合計」のことに他なりません。
で、現在の基準でそれを具体的にどう定めているのかというと、
建物の 1 階に作用する水平力を、建物の全重量の 20% とする
ことにしています。
これは結局、「 2 階の床位置での応答加速度が約 200gal である」としていることになります。注)
注)
重量とは質量に重力加速度( 980gal )をかけたものです。建物の全質量を m とすれば、全重量は 980 × m になります。水平力が建物の全重量の 20% である、ということは、その力が 0.2 × 980 × m であることをいいますから、この時の加速度は 0.2 × 980 で、約 200 です(重力加速度の値を最初から約 1000gal と考えた方が分かりやすいかもしれません)。
これまで、震度階がどうの、あるいは震度階と加速度の関係がどうの、というような話をしてきましたが、今まで対象としてきた加速度とは「地面の揺れ」、つまり「地動加速度」のことです。
となると、震度階と建物の耐震性能のことを明らかにしようとしたら、今度は「地動加速度と応答加速度の関係」を明らかにしなければならないことになります。
この関係を「一般的にこうである」というのは(たぶん)非常に厄介です。しかし幸いなことに、現行の耐震基準の解説書である「構造計算指針・同解説 1988 年版」(建設省住宅局建築指導課監修)という本を開くと下のような文章が見つかります( P.106 )。
この水平力を生じさせる地震動の強さは、地動の最大加速度にして 80 〜 100gal 程度である。
ということは、応答加速度が 200gal なのですから、2 倍から 2.5 倍程度の増幅率(応答加速度/地動加速度)を想定していることになります。
これが本当だとして、次に、この「80 〜 100gal 程度の地動加速度」を先の「河角の式」にあてはめて震度階をもとめてみると、この「中規模の地震」とは「震度 5 弱」である、ということになります。・・・あれ? 冒頭に掲げた国土交通省の回答では「震度 5 強」となっていました。なんかの間違いじゃないの?
・・・ということにもなりかねませんが、しかし、そういう詮索にはあまり益がありません。
国土交通省の回答の根拠になっているのは、地動加速度とか増幅率とかの話よりも、むしろ、
このような耐震基準にもとづいて建てられた建物の過去の被災状況を見てみると、震度 5 強程度の地震に対して大きな損傷を受けないことが実証されている
という「経験知」に重きをおいたものだと考えられます(もちろん、わたしの推測です)。
この「建物の総重量の 20% の水平力が作用する」という状態を地震の規模に厳密に関連づけようとするのは無益です(せいぜい言えるのは「おおむね震度 5 くらい」という程度)。なぜ無益なのかについてはすでに言いましたが、ひとつは「そもそも震度階と地動加速度の関係が明確でない」ことでであり、さらに「地動加速度と応答加速度の関係だって建物によっていろいろ違う」ことです。注)
注)
この「80 〜 100gal 程度の地動加速度」という表現は、どうも「あと付け」のような気配があります。少なくとも、かなりの留保を付けて受け止めておくべきものでしょう。それかあらぬか、この「構造設計指針・同解説」の実質的な改訂版となる「建築物の構造規定」(わたしの手元にあるのは 1997 年版)では、この記述は抹消されています。
ところで、この「建物の総重量の 20% の水平力をさせ、それに対して建物に損傷が生じないことを確かめる」という設計方法は、何も 1981 年から始まったわけではありません。1950 年に建築基準法が制定された時からのルールで、いわば半世紀の歴史をもっています。
ではどこが違うのかというと、1981 年までの耐震設計は「これで終わり」だったのです。
しかしよく考えてみると、それまでだって震度 5 を超える大地震は何度か起きており、実際に建物が被害を受けてもいました。にもかかわらず、「中規模の地震」については考えるが「それ以上」のことは考えない、という立場をとり続けたのはなぜだったんでしょう?
ひとつには、「建物が損傷しないことを検証する手法は確立されていたが、建物が倒壊しないことを検証するための汎用的な手法が確立されていなかった」という実際的な事情があげられます。しかし、それよりも大きな比重を占めたのは、ここでもやはり「経験知」です。
そのあたりの事情は、前掲書「構造設計指針・同解説」に以下のように書かれています( P.106 )。
昭和 56 年 5 月まで用いられてきた建築基準法・同施行令でいう水平震度 0.2 に対し許容応力度設計するという耐震計算法 注) は、約半世紀の歴史を持ち、通常の多くの建築物についてはこの方法で設計しておけば計算外の余力が十分にあって、大地震に対しても崩壊しないという経験を持っている。
注)
「水平震度 0.2 に対し許容応力度設計するという耐震計算法」というのは、これまで述べてきた設計法と(いくつかの細かな違いはあるものの)大筋においては同じものです。
この文章から分かるのは、「中規模の地震(震度 5 程度)に対して損傷しないように建物を設計しておけば、それより大きな地震がきても、(損傷を受けたり部分的に壊れたりはするものの)建物の倒壊にまではいたらない」ことが「経験的に証明された」という事実です。だから「これで終わり」でよかったのです。
しかし諸々の研究により、建物が倒壊しないことを検証するための汎用的な手法が確立されたので、これを機に「最後まで(つまり建物が倒壊にいたるまで)検証することにしましょう」となったのが 1981 年だったのです。この「倒壊にいたるまでを検証する」とは、上の引用文にいう「計算外の余力」を具体的に跡付ける作業に他なりませんが、次はその話です。
3-2. 大規模な地震
これは「極めてまれにしか発生しない地震」と説明されていますが、どんなものかを手っ取り早くいえば「阪神淡路大震災クラスの地震」です(ひと昔前ならば「関東大震災クラス」といいました)。もう少し詳しくいえば、「そのような地震に遭遇する確率は低いが、しかし遭遇する可能性を否定できない、これまで経験した最大級クラスの地震」です。
中規模の地震に対しては建物が「損傷しない」ことを目標にしましたが、この地震に対しては建物が「倒壊しない」ことを目標にします。
もちろん、このような大地震に対しても「損傷しない」ように設計することは可能ですが、場合によっては、多大の費用をかけて原子力発電所のようなマンションに住むことにもなりかねません(今では「免震」「制震」という選択もありますが)。ようは費用対効果の問題で、どこかで「そこそこに妥協する」わけですが、現行の耐震基準では、その妥協点を、
そのような(何百年に一度という)大地震によって建物が部分的に壊れることは甘受する。しかしその場合でも、建物全体が壊れて人命が危険にさらされるような事態だけは避けておこう。
というところに見出していることになります(もちろん、これは「最低限の要件」ということですが)。
ところで、中規模の地震に対してはしきりに「損傷」という言葉を使い、ここではさかんに「壊れる」という言葉を使っています。
前項で、柱・梁・壁などの骨組が「損傷する」とは「亀裂が入る」状態のことだと言いましたが、これに対して「壊れる」とは「鉄筋がすっかり伸びきってしまう」ことを言います。視覚的なイメージとしては、「コンクリートが剥落して中の鉄筋が見えるような状態」を思い浮かべていただければいいと思います(たぶんそういう写真なり映像なりをどこかで目にしているはずです)。
ただしここで注意したいのは、たとえ一本の梁・一本の柱が壊れたからといって、それで建物全体が壊れる(これを「倒壊」あるいは「崩壊」と言います)わけではない、ということです。
たとえば下図のような柱・梁からなる三階建ての骨組についていえば、この骨組全体が倒壊するためには、ここに×印でしめしたようなすべての部位が壊れなければなりません(これは力学的に証明できます)。「一本の梁が壊れる」から「建物全体が壊れる」までの間には結構長いプロセスがあるのです。
建物が倒壊にいたるまでには下のような三つのプロセスがあります。
状態 1 柱・梁・壁が「損傷する」
↓
状態 2 柱・梁・壁が「壊れる」
↓
状態 3 建物が「壊れる」(倒壊する)
前項に述べた中規模の地震と関連づけられているのが「状態 1 」で、今回の大規模な地震と関連づけられているのが「状態 3 」です。
さきほど述べたとおり、この「状態 1 から状態 3 へ」と移行するプロセスは「結構長い」のですが、この「結構長い」という事実が、前項の最後の方で引用した文中にある「計算外の余力が十分にあって」という言い方の根拠になっています。何なのかというと、
普通に設計された建物の場合、「状態 1 」をもたらす地震のエネルギーと「状態 3 」をもたらす地震のエネルギーには数倍程度の開きが出る。つまり、建物の倒壊という事象に対しては最初からそれだけの「余力」をもっている。
だから、中規模の地震に対して損傷を受けないように設計しておけば(状態 1 )、特に意図しなくても、その数倍程度のエネルギーをもつ大規模な地震がきても倒壊(状態 3 )までにいたることはない。
ということです。そして、それが今までの大地震の経験から実証されてきた、ということをさきほどの文章は言っていたわけです。
しかし、そのような事実は認めるものの、「やっぱり最後まで検証しよう」ということになったのが 1981 年に定められた耐震基準である、ということもすでに前項で述べました。そしてこれから話そうとしているのは、「それが具体的にどんなものなのか」です。
この地震に対する検証に当たっては、
中規模の地震の時の 5 倍のエネルギーに相当する力が建物に作用した状態
を考えます。
中規模の地震の時は 200gal の加速度が建物に作用するものとしましたが、これを単純に 5 倍すると 1000gal(つまり 1G )になります。ですが、これを「 1000gal の加速度が建物に作用した状態」と言わずに、なぜか突如「エネルギー」などという言葉を持ち出してきました。これは、大地震の検証にあたっては、建物の「エネルギー吸収機構」というものを考えているからで、
大地震に対して建物が「壊れない」とした場合は 1000gal の応答加速度が生じることになるが、壊れた場合は、その結果として建物のエネルギー吸収機構がはたらき出し、応答加速度は 1000gal よりも小さくなる
のです(建物の状況にもよりますが、だいたい 1 / 2 から 1 / 3 程度に力が減殺されます)。注)
注)
建築工学上では、部材が「壊れる」という状態を必ずしもネガティブなものとしては捉えていません。大地震の時に壊れるのはある程度しょうがないが、ただし健全な壊れ方をさせよう、という考え方をとります。
「健全な壊れ方」とは、「壊れた後に、その部分が関節のように回転して変形についていく」状態です。これを「粘りがある」と言ったりしますが、その反対は「もろい」です。「もろい壊れ方」とは、たとえば壊れた梁がそのまま下に落っこちてしまうような状態です。
大きな地震がきて「健全な壊れ方」が進んでいくと、建物のあちこちに「関節」ができた状態になります。そうすると建物が全体として「柔らかく」なり、それに伴って建物の変形(揺れ)は増大します。しかしその反面、地震の力を「やり過ごす」という機構が建物に生まれてくることになります。
つまり、建物が柔らかいサンドバッグのような状態になって地震のパンチ力を吸収し、それを一部減殺するのです。
まあ、それはともかく、ようするにこの地震の大きさは中規模の地震の 5 倍くらいのものなんですが、となると、先ほどと同様、「それはどの程度の地震なのか」という話になります。これについても前掲書「構造設計指針・同解説」に書かれています( P.106 )。
その強さは、地動の最大加速度で約 300gal から 400gal 程度で、気象庁震度階の震度 6 〜 7 程度 注) である。
注)
この本が出版された当時は、気象庁の震度階に「 5 弱・ 5 強・ 6 弱・ 6 強」という区分がありませんでした。
ここにある最大加速度と震度階の関係は、おそらく河角の式によっているものと推測されます。先に述べたとおり、現在ではこの式の妥当性がかなり疑われているらしいので、ここに書かれている最大加速度と震度階の関係についてはいくぶんの留保が必要ですが、しかし、このようにして設計された建物の耐震強度の妥当性がその後の阪神淡路大震災によってかなり証明された、ということも事実なのです。
4. 震度5強で倒壊の恐れあり
さて、これでようやく、本コラムの表題に使わせていただいた「震度5強で倒壊の恐れあり」というコメントに戻ることができます。
冒頭で紹介したように、これは Qu / Qun 、つまり「保有水平耐力/必要保有水平耐力」という指数を根拠にしています。それぞれの値が何を意味するのかは、前章の内容からおおよそ理解できるかと思います。
「保有水平耐力」とは、「建物を倒壊にいたらしめる力の大きさ」あるいは「倒壊しようとする瞬間に建物に作用している力の大きさ」です。これに対して「必要保有水平耐力」とは「大地震の時に建物に作用するであろう力の大きさ」です。
そしてこの「大地震」とは、国土交通省のコメントによれば「震度 6 強から 7 程度」であり、河角の式あるいは前掲書「構造設計指針・同解説」の内容を信じれば、「地動の最大加速度で約 300gal から 400gal 程度」です。
となると、この指数が 0.5 であるということは、耐震基準で定める上記の力の半分になりますから、この建物は「地動の最大加速度で約 150gal から 200gal 程度」で倒壊にいたることになります。
これを再び河角の式によって震度階に戻すと「震度 5 強」です。だから、国土交通省は「震度 5 強で倒壊の恐れあり」という表現を使ったのです(たぶん)。
ただし、ひとつ難点をあげれば、ここには、今までしばしば強調してきた「経験による裏付け」「経験知」はありません。なにしろ、そのような設計が行われた建物が大地震に遭遇した、という事例をわたしたちは今まで知らないのですから(もちろん、「幸いにして」というべきですが)。
最後に補足(もしくは蛇足)をひとつ。
前章で「1981 年以降、建物の倒壊にいたるまでの検証が行われるようになった」と言いましたが、じつは、これは正確な表現ではありません。
現行の耐震基準でも、建物の高さが 31m 以下で、かつ一定の条件を満たすものについては倒壊の検証を省略してよいことになっています。つまり、前章で説明した「計算外の余力」に頼ってよいとされています。
そして、そのようにな設計がなされた建物に対して建物の倒壊にいたるまでの検証をあらためて行った場合、つまり「計算外」を「計算内」に引きずり出した場合、そこで OK という結果が出る保証は必ずしもありません。
したがって、国土交通省が公表している資料の中に、もしそのような(倒壊の検証までを必要とされていない)建物が含まれていて、それに対しても「耐震強度が足りない」と言っていたとしたら、それはおかしな話になります。その建物は「法令のとおりに設計されているが耐震強度が法令を満たしていない」という奇妙な立場に置かれることになるからです(ただし、実際にそのような建物が含まれているかどうかについては、公表されていないのでよく分かりません)。
(終わり)